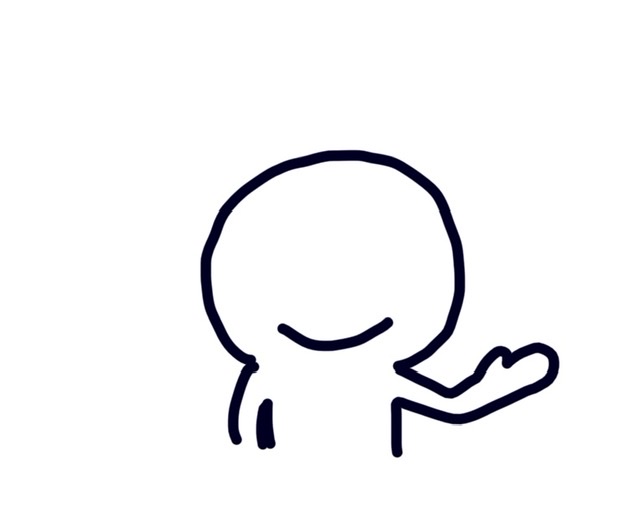
いらっしゃいませ 地図屋でございます。
本日は2025年11月1日(土)道標日記No.529です。 ご来店ありがとうございます。
今年もあと2ヶ月になりました。本当に月日の経つのは早いものです。
・・・と、ありきたりな挨拶から始まりましたが、正直、月日が経つのが早いとはそこまで実感がなく、同じようなことを言い、共感しあっているが、何か“中身”のないような言葉に聞こえるのが、相変わらずの天邪鬼な私です。
さて、先日、狩猟免許に無事合格し、狩猟免状を受け取った私です。しかし、そこから狩猟者登録をするわけでもなく、狩猟を本格的に始めるわけでもないので、ちょっと次の目標がなくなったような心持ちでいる今です。
ここから考えているのは、猟師の師匠に捕まえた猪や鹿の解体を見せてもらったり、もしかしたら罠の設置に同行させてもらえる?と、1人で思っているところです。
しかし、頭に浮かぶのは“熊”のことなんですよね。
熊の被害のニュースに、山に入ることに躊躇している私がいます。ただ、熊のニュースばかり見すぎて、“恐れすぎている”自分がいること、けれど、必要なことだからと、その情報を自分の中に取り入れすぎてしまい、それが“正しい”と思い込んできている状態の自分を感じています。
情報の怖さはこんなところにあるのでしょうね。皆を同じ考えや方向に導くこともできるし、正しいと思わせることもできる。だけど、今の社会で情報は不可欠なものになっている。
科学の進歩とともに、人間はものすごい力に取り憑かれてしまっていると思います。しかし、抜け出すことはもうできず、正しく読み取る力が必要なんて言われますが、その必要性をどんどん超えて膨らみ続けているのも人間の手によって行われていると思うとやるせなくなる時があります。
そんなことばかり考えていたら、また何もできなくなる自分がいるので、“今日も自分の人生の最善を尽くす”ことに意識を戻して臨んでいきます。
さて、またまたまとまりのない挨拶になってしまいましたが。
寒さは日々増していきます、皆さま、どうぞご自愛くださいませ。心も身体も元気でいることが何よりです!
今回の道標日記は
☕️よりみち 【 なぜ“この道”を歩んでいるのか 】 その④
を紹介させていただいております。
私の習慣が、皆さまの夢のお手伝いになれば幸いです。
夢への地図を描くお店 World Map 5 🗺 どうぞ ゆっくりしていってくださいね😌
☕️よりみち 【 なぜ“この道”を歩んでいるのか 】 その④
🪧その④ 次、目指すものは?
ニュージーランドに行く目標が早くも叶ってしまった(現実を突きつけられた)私は、次の道がわからなくなりました。
🪧ニュージーランドに一緒に行った人たちのように研究者の道へ行くか
🪧実践者に戻って、勉強しつつ、保育を先導(ちょっと偉そうな言い方ですが)する道に行くか
歳も歳なので、チャレンジできる機会は減っていき、それが焦りにもなっていました。
しかし、ニュージーランドに行き、そして、その後も色々な保育・教育の現場に行く機会があり、ふと思ったことがありました。
“保育”とはいったいなんなのだろう と。
ニュージーランドでは素晴らしい保育の現場、尊敬できる実践者・研究者に出会うことができました。一方で、社会や大人が求めることに応えるための“サービス”のような保育にも出会いました。それは日本の保育現場でも見たことがあるものでした。
グローバル社会になり、皆が情報を簡単に手に入れられるようになった今、どこかでその情報が操作され、皆が“同じもの”を目指してしまうのではないかと私の中では危惧するところがありました。操作されていなくても、輝かしく“付け加えられたもの”“加工”されたものに惹かれて、皆が同じものを目指してしまうのではないかとも思いました。
私は保育現場も同じようになっている気がします。それが子どもの幸せだと信じ、付け加えることに必死になっていく。理想の子どもに仕上げていくこと、それが保育なのでしょうか。
私は、せめて、乳幼児期は、子どもには子どもらしく過ごしてほしい、と思いました。それが保育なのではないかと思っています。しかし、大人にとって、社会にとって都合のいい人間になるためになってはいないでしょうか。
保育がわからなくなった時、そのヒントをくれたのはやはり“子ども”でした。
加工されず、“与えられた夢中”ではなく、うちからでる“ほんものの夢中”を持って生き生きとしている子ども。そんな子どもに出会うのは、大人の物差しの少ない“自然”のなかでした。それは保育の場で、そして我が子からも感じ取れました。
しかし、私は自然を避けてきた人間(デジタルなど)なので、自然の中で過ごす子どもを“知る”“みつける”ことができないと考えました。
そんな時、浮かんだのが、あるお子さん、そしてそのご家族である“猟師”だったのです(詳しくはWonder journey【加工されていない世界へ】で)
そして、私は“猟師の世界”へ向かい始めたのです。
次回は最終回、道標日記🪧No.532 人として生きる 狩猟の道 を綴らせていただきます。



👂今週のおすすめ耳勉強・動画

👂今週のおすすめ耳勉強はコチラ🫱 👂
RehacQ SP 『 旅と人生 』
RehacQ SP 『世界の果てに、くるまおいてきた まったり雑談配信 』
RehacQ SP 『 激論!クロスファイア なぜ番組終了? 』
Geotaro_Sketchbookさん
FUKUさん 『 2025秋のカインズアウトドア用品 』
両学長 『 Webライティング 』
フェルミ漫画大学さん 『 移動と階級 』
本要約チャンネルさん 『 その習慣、変えてみたら? 』
RehacQ SP 『 社会人のための「死」入門 2025 』
ぎわちんさん 『 ゴジラ一番くじ 』
RehacQ SP 『 斎藤幸平さん・志位和夫さん 対談 』
HTB News 『 猟友会“出動拒否” 』
ABEMA Prime 『 市街地に熊が・・・。』
山と渓谷ch 『 熊とともに生きるために 』


地図屋さんの夢を叶える習慣 夢活シリーズ2024はコチラ🫱

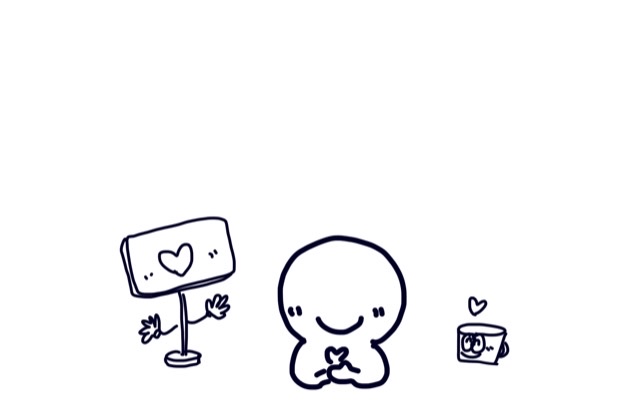
World Map 5の最近の購入もの

本日もご来店ありがとうございました。
毎日が皆様にとって素敵な日になりますように
それでは
Have a nice dream day.🎫✈️
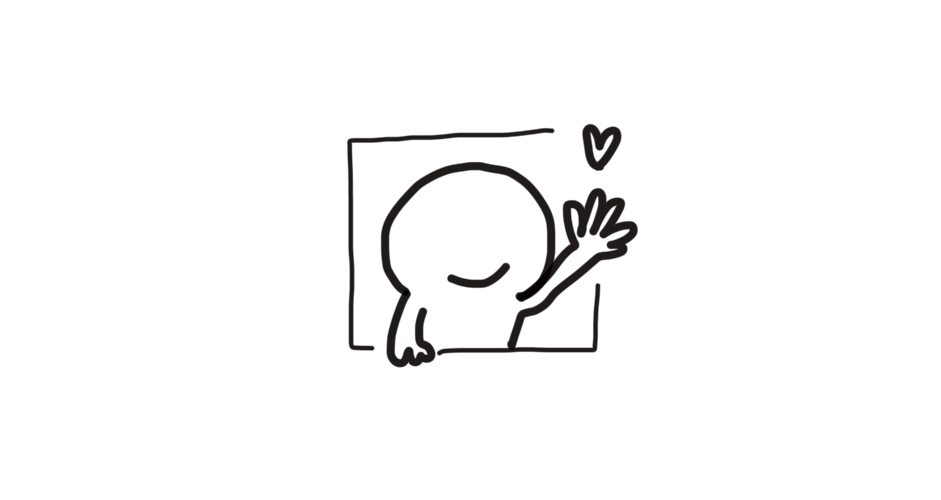
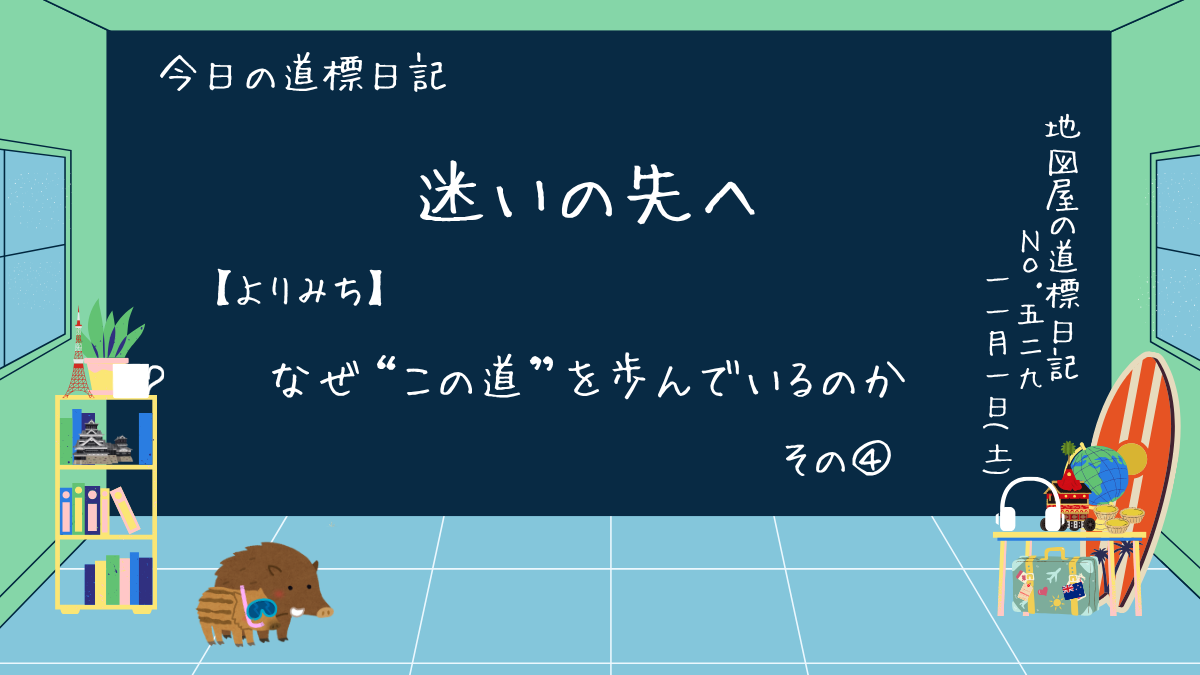
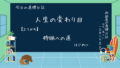
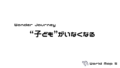
コメント