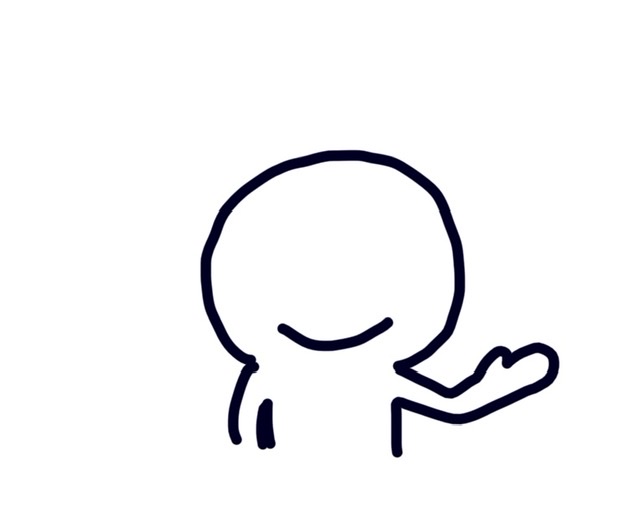
いらっしゃいませ 地図屋でございます。
本日は2025年10月11日(土)道標日記No.526です。 ご来店ありがとうございます。
運動会シーズンですね。私の周りでも、我が子の体育祭、区民体育祭などが行われ、“行事”というものを感じております。
前回の道標日記で季節の周期“季まま”と、大人がまとう“気まま”のズレについて綴らせていただきました。少しずつ涼しくなって過ごしやすい時期にゆっくりと流れる季に、人間のつくった流れが時に子どもを苦しめていることもあるのではないかと、その時は考えました。
そう感じた時から1週間が経ち、今は、子どもは柔軟に大人の“気まま”に合わせていっているように感じました。これは良い意味でも悪い意味でも。
スポーツの秋とは言いますが、確かに身体を動かしやすい時期であり、人間も本能的なのでしょうか、活発になったり、実る物も多い季節なのでの食欲が増す(食欲の秋)とも言われています。これは冬に向けて身体がそうなるのでしょうか。そう考えると、人間の中に“季節”があるように思います。
そこから派生してというか、人間の暮らしに合わせて生まれてきたのが“行事”なのであれば、私の感じているズレというものはないのでしょうね。そう思うと行事は人間の生活の“彩り”になるのでしょう。人間の細胞にある“季節”と行事については今後の研究にしていきたいと思います。
しかし、柔軟にそのズレに合わせていける人もいれば、そうではない人もいます。行事が人間の中の四季と離れ、能力や成果が問われるだけ、またそちらに重点を置いたのものだと捉えると、苦しいものになる。そう感じている人がいるのも見受けられます。その見方も、私たちの染み付いて文化がつくってきたものなのでしょうね。
何についてもそうですが、始まりには願いが込められていますが、次第に薄れ、かたちだけが残るものがあります。
彩りとして始まった“行事”の意味を、その時期に置かれた時にこそ考えることが大切になるのではないでしょうか。
さて、いつもながらまとまりのない挨拶になりました。
今回の道標日記は
🗺️My Wonder journey 【 “子ども”がいなくなる 】 その③ 壊れていく子ども
を紹介させていただいております。
私の習慣が、皆さまの夢のお手伝いになれば幸いです。
夢への地図を描くお店 World Map 5 🗺 どうぞ ゆっくりしていってくださいね😌
🗺️My Wonder journey 【 “子ども”がいなくなる 】 その③

こちらは旅する保育者としての私が、日々の保育や学びのなかで生まれた“不思議”“問い”をつづる場にしたいと思い始めました。常に問いとそれを探求する思いを持ち、保育者として成長し続けたいです。
今回は、【 “子ども”がいなくなる 】です。
その③ 壊れていく子ども
“こども”がいなくなる 最後の章は、壊れていく子どもです。
子どもが壊れていく その1つ目の原因から。
・外で遊べなくなる
私は保育現場で働いていますが、夏になるとあることに悩まされています。それは、“暑さ”です。年々、気温は上昇し、最高気温が更新され続けています。熱中症警戒アラートというものができたのはまだ最近。夏の暑い日に、小さい体である子どもが外で遊ぶことは“危険”というのが、もう常識になっています。
晴れて、蝉が鳴き、今日は散歩に行きたいなと思っても、警戒アラートが28℃を超えていたら外にいくことはできない決まりになっています。もちろん小さい子どもにとっては命にも関わることので、子どもは外に出ず、ずっと室内で遊び続けることになります。年々、暑い時期が長くなっています。運動会の練習ができないから、運動会の日を10月後半にした園もあるほど。それぐらい、子どもは“外で遊ぶ”機会が少なくなっているのです。自然と離れ、閉じ込められた世界で、子どもは育つのでしょうか。この時期に育つ子どもの力を育てることができない。このことは子どもが壊れていくのではないでしょうか。
・デジタル
2つ目は、デジタルです。
親のスマホで動画を見たり、ゲームをしたりしている子どもを見かけたことはないでしょうか。“スマホ育児”と言われるものです。子どもは手が短いのでスマホの画面を離すことができず、顔の近くにスマホを置いて観ています。親もスマホがあることで、スマホができる以前よりも子どもと向き合う時間は格段に減ったと思います。(私もそうです💦よくパートナーや我が子に怒られます)
スマホだけでなく、デジタル社会により、便利になったことは様々な“不便さ”をなくし、手を出せば水が出て、トイレでは立ち上がれば水が流れ蓋が閉まります。何かを得れば、その対価を支払うように、人間から“何かを失っている”ような気がします。
これは耳勉強でも学んだ“ドーパミン中毒”にもありましたが、デジタルは簡単に“快楽”を手に入れることができ、それはいずれ中毒脳をつくり恐れがあります。小さいことから衝動的に快楽だけを求め続けるような環境で育つ子どもたちはどうなるのでしょう。
今はAIという人工知能が当たり前のように社会の中にあります。これにより、私たちの生活はまた大きく変わるでのはないでしょうか。そして、その大人がつくった“セカイ”で育つ子どもは、今よりも“壊れた”子どもになるのではないかと危惧しています。
・食べもの
食べ物も子どもの育ちに重要なものです。これは、もう前から言われていることなので、ここで綴る必要はないかもしれませんが。私たちの口にする身近なものは、加工されているものが多いです。それを口に入れて影響が大きいのは、小さく、いま育とうとしている子どもたちです。それらの加工されたものは、あることが“当たり前”になり、食べることが“当然”になっているので、抵抗感なく子どもに与えるものとなっているように感じます。
デジタルも加工された食品も、取りすぎると身体に悪いことがわかってきています。しかし、その情報を手に入れる機会は少なく、メディアで取り上げられることも少ないです。それはやはり“お金”が絡んでいることであり、子どもだけでなく人よりも金儲けが優先されている現状があるのではないでしょうか。
結語 と 今後のWonder
ここまで、“子どもが壊れていく”と書きましたが、これは今に始まったことではなく、人類の歴史の中で“今”に至っているのだと思います。便利に豊かに生きたいという人間の本能とも言える欲求が“今”をつくってきたのです。
今回のWonderも“子どもがいなくなる”ですが、進歩により、子どもが“子どもらしく”になったところもあるでしょう。日本で言えば社会保障や義務教育の整備、人権保障の理念の発展などがあると思います。
それらも含まえて、“今”できることを考えていかなければならないと思います。より“子どもが子どもらしく”なれる社会をつくっていくことが大人の責任であり、保育者の責務だと考えます。
今回のWonderを綴り始めた時は、
「もうこのままでは子どもが子どもらしくいるなんて無理だ」「長い歴史の中で今に至っているのだから、この流れには逆らうことはできない」なんてマイナスのことばかり考えてしまっていました。しかし、最後の最後ので、子どもにとってよくなっているところもあると思えたことが、自分の中で希望を持てることとなりました。
子どもがより子どもらしくなれる社会のために尽力し続ける これを今後の私に課題“Wonder”にしていきます。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
では また👋

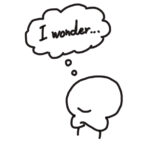
旅する保育者 地図屋のMy Wonder Journeyはコチラ🫱

👂今週のおすすめ耳勉強

👂今週のおすすめ耳勉強はコチラ🫱 👂


地図屋さんの夢を叶える習慣 夢活シリーズ2024はコチラ🫱

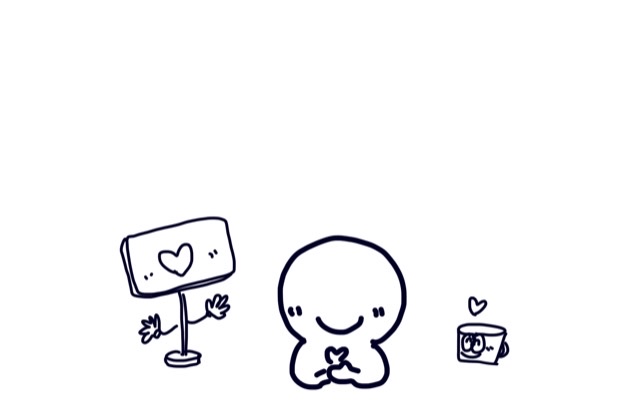
World Map 5の最近の購入もの
🧹必要なものはそれほど多くない。掃除をするとそれはよくわかる

本日もご来店ありがとうございました。
毎日が皆様にとって素敵な日になりますように
それでは
Have a nice dream day.🎫✈️
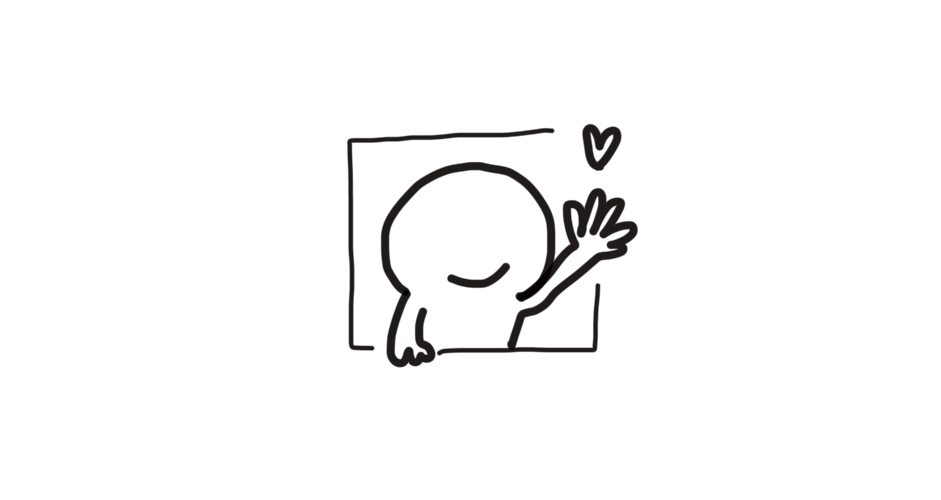

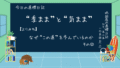
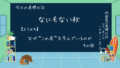
コメント