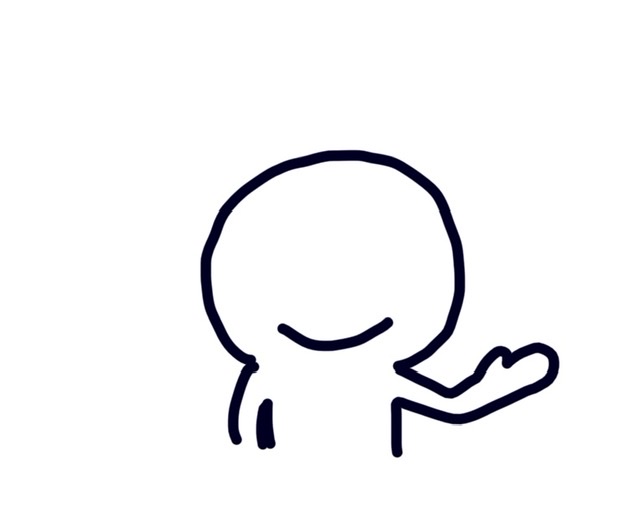
いらっしゃいませ 地図屋でございます。
本日は2025年8月9日(土)道標日記No.517です。 ご来店ありがとうございます。
今回の日記のタイトルは『 新しい道へ 』です。実は今日、新しい保育現場の面接があるのです。その園は保育書籍にも載っている園で、その園の保育者の方々は研究会も一緒なのです。
その書籍を読んでいて、その保育現場に入りたいと考え、園長先生に相談したところ、まずは月1回の土曜日からということにさせてもらい、今日、面接をさせてもらうことになりました。
その園は私の住んでいる地の隣の都道府県になり、車で1時間かかるところにあります。通勤時間1時間かと思うと少し気が滅入るところもありますが、せっかくいただいた学びの機会なので、自身の経験にしていきたいです。
そして、今日は長崎の平和の日です。80年が経ちました。この季節になると平和について考えます。考えることができることは幸せであり、これを続けていくことが大切だと考えます。
正直、私は平和のためにやっているは“考える”だけです。それを、家族や職場の仲間と話すだけに至っています。ここに綴れるようになったこともこれまでの自分から一歩進んだと書きながら思っています。
ただ、ただ、生きる
最近、そう思うことがあります。
多くを求めず、すでに満ち足りていることに気づき、生きていられる、他によって共に生かし合っていることに感謝していきたいです。
さて
今回の道標日記は
🗺️My Wonder journey 【 保育を育てるもの 】 その②
を紹介させていただいております。
私の習慣が、皆さまの夢のお手伝いになれば幸いです。
夢への地図を描くお店 World Map 5 🗺 どうぞ ゆっくりしていってくださいね😌

平和の絵本
👂今週のおすすめ耳勉強

👂今週のおすすめ耳勉強はコチラ🫱 👂
フェルミ漫画大学さん
ピース又吉さん
リハックさん
広島のお好み焼きが食べたくなる🤤
🗺️My Wonder journey 【 保育を育てるもの 】 その②

こちらは旅する保育者としての私が、日々の保育や学びのなかで生まれた“不思議”“問い”をつづる場にしたいと思い始めました。常に問いとそれを探求する思いを持ち、保育者として成長し続けたいです。
今回は、【 保育を育てるもの 】です。
その② 育てなくてもできてしまう保育
前回は保育を育てにくい“構造”について綴らせていただきました。
今回は、“育てなくてもできてしまう”保育についてです。
これは、保育者が別に変わらなくても、そのままの保育をやっていても問題が起こらない(みえない)といったら、ちょっと乱暴かもしれません。
・過去と同じことをやっていれば良い
歴史のある保育現場であると、一年の流れが大体決まっています。七夕やクリスマス、節分などの季節の行事や、運動会や生活発表会などの園行事とよばれるものがあります。
職員同士で話し合い、今年の行事・取り組みについての会議をしますが、どこか“例年と同じことをやっておけばいい”という雰囲気があります。
園の行事だけでなく、保育もですが、つくられた・やり始めた時は、その時の保育者や子どもの願いが込められているものだと思っています。「子どもにこんなことをさせてあげたい」「こうしたら目の前の子どもたちにそぐっているのではないか」など。それはとても大切なことであり、その時の子どもたちと保育者とのが考え合った“最善”のかたちだったのだと思います。
しかし、月日が経つと、そのかたちは残りますが、願いは薄れていきます。「去年もやってよかったから」と、大人(保育者や保護者)の中だけで“美化”されていき、「じゃあ今年もやろう」となります。これが“過去と同じことをやっていれば良い”という保育が育たない原因の一つとなっていきます。
本当に“今”目の前にいる子ども達への“最善”なのでしょうか。例年と同じことをするにしても、“願い”を深掘りすることをおざなりにしてはいけないと思います。
これは行事だけでなく、その園の環境が生むものもあります。それは保育のかたち(年齢構成、子どもの人数、職員の人数、規模、部屋数、園庭や給食室の有無、園がある土地の風土など)によって違ってきます。ルールであったり、導線、また、暗黙の了解の部分があるかもしれません。
それらが保育の“常識”としてあると、なかなか変えづらいものがあります。
“常識は思考停止”ということばがありますが、考えなくても良いのが果たして本当に子どものためなのでしょうか。
・文化が育てているものに気づくことも大切
しかし、“変わればいい”というわけでありません。その園の保育が積み上げてきた“文化”は子どもにとって財産でもあります。
最近読んでいる本📕『人はいかにして学ぶのか』では
「文化の与える制約的条件のおかげで、人びとは容易かつ速やかに学ぶことができる」
と、あります。
これを、今回のWonderに合わせて私的に解釈をすると、
“その園の積み上げてきた文化は、知らず知らずのうちに子どもにとって最善の機会を与えている”ともいえるということです。歴史とともに積み上げてきた人間関係、地域との交流などの社会的資本(人と人との関係を資本として捉える考え方)も、その園の歴史や文化に当てはまるかもしれません。
園の保育を育てることために変化を促すことも大切ですが、その園の気づかない・当たり前になっている“文化”の中にある“子どもへの最善”を失わないようには気をつけなければならない、と、この本と出会って再考したことでした。その逆も然りですが。
さて まとまりがなくなってきましたが 笑
今回は“育てなくてもできてしまう保育”について綴りました。
次回が最後になります。最終回は
“そもそも育つことをしない”について綴らせていただきます。
最後までお付き合いいただければ幸いです。

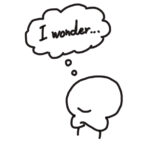
旅する保育者 地図屋のMy Wonder Journeyはコチラ🫱

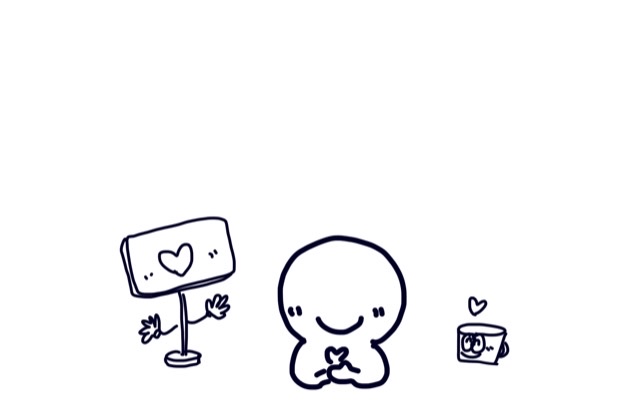
World Map 5の最近の購入もの
今週はありませ〜ん





ポケモンGOの師匠 学習ドクター松本先生の今週の動画はコチラ 🧑🏫

本日もご来店ありがとうございました。
毎日が皆様にとって素敵な日になりますように
それでは
Have a nice dream day.🎫✈️
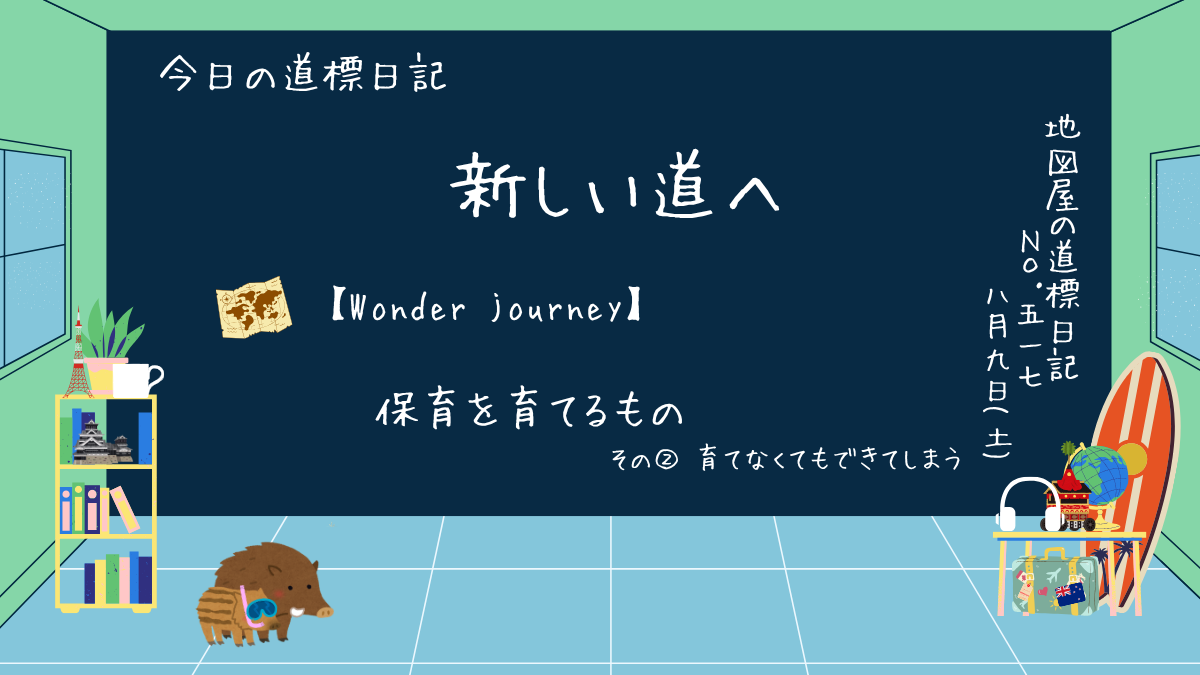
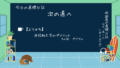
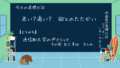
コメント