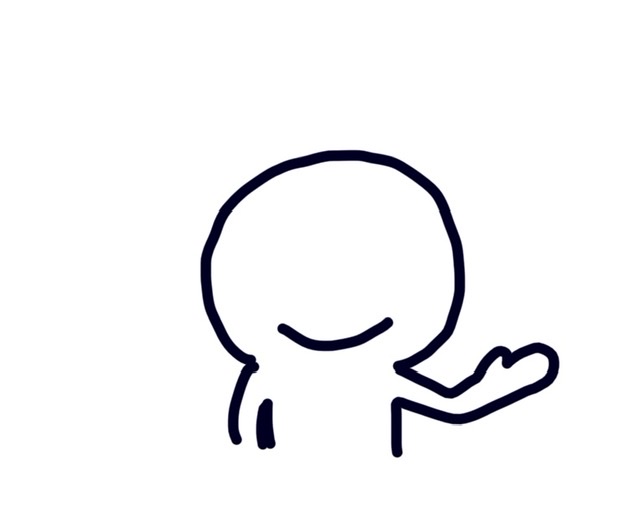
いらっしゃいませ 地図屋でございます。
本日は2025年7月26日(土)道標日記No.515です。 ご来店ありがとうございます。
本日は狩猟の師匠たちと海へ行く日です。ワクワクしている私です。
今年から狩猟に興味を持ち始め、そして運命的な巡り合わせのおかげで、狩猟家族との再会を果たしました。
私は、今こそ、保育に“自然”が必要だと感じています。しかし、“自然”を必要ないと避けてきた私自身が“自然”を知らないのです。そこで興味を持ったのが自然と共に暮らす“狩猟”の世界です。
このご家族に出会い、そしてこれからいろいろなことを教えてもらいたいと思っています。それが私の保育を豊かにすると考えています。今回は魚突き、そして、これからは狩猟や解体なども教わっていきたいと勝手に思っています😅
狩猟免許の勉強も進んでおります(できる時だけになっていますが💦)
今年はチャレンジの年だと思っていますので、行動しまくって道を拓いていきたいです。
さて
今回の道標日記は
☕️よりみち 【 通信制大学のデメリット 】 その① 対面ではない
🗺️My Wonder journey 【 保育を育てるもの 】 その① 保育を育てにくい構造
を紹介させていただいております。
私の習慣が、皆さまの夢のお手伝いになれば幸いです。
夢への地図を描くお店 World Map 5 🗺 どうぞ ゆっくりしていってくださいね😌
👂今週のおすすめ耳勉強

👂今週のおすすめ耳勉強はコチラ🫱 👂
フェルミ漫画大学さん
東出昌大さん
両学長さん
学習ドクター松本さん
リハックさん
中田敦彦さん
☕️よりみち 【 通信制大学のデメリット 】 その①

通信制大学に通う地図屋さん。
今回の☕️きょうのよりみちでは、地図屋さんが感じる通信制大学のデメリットを紹介させていただきます。通信制大学に通いたいと思っている方の参考になれば幸いです。
その① 対面ではない
ここからは通信制大学のデメリットを綴っていきます。
まず1つ目は、“対面ではない”ということです。
そんなの通信制大学なのだから当たり前じゃないか、と言われそうですが、私は、それがメリットでもありデメリットでもあると考えています。ではなぜ“対面ではない”ことがデメリットなのでしょう。
“人”が紐付けられない 先生も友達もいない
通信制大学は、基本、1人で勉強を進めるものです。
レポートであれば、インターネットで大学のサイトを開いて、シラバス(講義や試験で扱う内容の全体像を記したもの)と読んで、テキストをネットで購入し、テキストを読み、パソコンでレポートを書いていきます。参考文献の論文もネットで集めます。
スクーリングであれば、講義を一緒に受ける人が複数おり、ディスカッションで同じグループになることがありますが、そのスクーリング期間だけの付き合いになります(1日で終わるものも。私でも最高3日間)
レポートは誰にも合わなくても準備からレポートの提出までできてしまいますし、スクーリングだってその日だけの付き合いなので忘れていってしまいます(私の記憶力が無さすぎるのもありますが😅)
そうなると、その授業に“関わる人”が浮かんで来ないのですよね。
私は大学の通学過程も卒業しているので、授業名とそれを担当する先生がやはり浮かびます。どちらかというと先生の方が先に浮かぶかもしれません。
一緒に受けた友達を浮かべることもあります。受けた教室もやんわりと思い出すことも、そして、どんな態度で授業を受けていたかも(笑)出席数を意識したり、試験の内容を友達に教えてもらったり。そんな授業以外の内容も含めて、思い出される“おまけ”が多いのです。それは、ある意味、その授業の“厚み”をつくっているものでした。
通信制大学にはそれがないのです。授業名を見ても、先生の顔も浮かびません。調べたら出てくるかもしれませんが、声も人間性も浮かばないのです。友達に至ってもそうです。一緒に学んでいる人がいないのですから、その授業の“厚み”が自分の人生の経験として残らないのです。


🗺️My Wonder journey 【 保育を育てるもの 】 その①

こちらは旅する保育者としての私が、日々の保育や学びのなかで生まれた“不思議”“問い”をつづる場にしたいと思い始めました。常に問いとそれを探求する思いを持ち、保育者として成長し続けたいです。
今回は、【 保育を育てるもの 】です。
その① 保育を育てにくい構造
さて
こちらもWonder Journeyコーナーでも保育が育てにくい理由を綴っていきます。
まず1つ目が、そもそも保育現場というのは“保育を育てにくい構造”をしていることです。(これは私の経験をもとにしていますので当てはまらない現場もあるかもしれません。ご了承ください。)
・研修を複数人で受ける保障がされていない
私の保育園では、研修があります。研修には都道府県、市町村、所属団体、大学、研究団体、企業など様々な研修があり、新人、中堅、管理職、研究生など、その人に合わせた研修を用意する場合もあります。
その研修は勤務時間内・勤務時間外で行われるものがあります。また、土日や祝日に行われるものもあります。
園から研修を受けるように言われているのなら、まだ良い方かもしれません。それが園の保育を育てるためのものならですが。
勤務時間内の研修であると、保育現場から保育者が出ることになります。現場が欠ける分はフリーなどの職員が入りますが、必ずしも体制の保障があるわけではありません。そんな余裕のある現場は少ないのではないでしょうか。また、研修に出せたとしても1〜2人ぐらいのもので、複数で受けることはほとんどできません。大体、1人で研修を受けて、報告書を書いて、会議などでちょっと共有しておしまいではないでしょうか。このフィードバックの薄い構造がが“保育の育ちにくさ”につながっているとも感じます。
・女性が多い職場
このパートは言葉を選ぶところもあるのですが、綴っていきます。
保育現場は男性保育者も増えてきたとはいえ、そのほとんどが女性保育者です。
女性の場合、産休があったり、子どもが生まれた場合、我が子・家庭中心の生活になります。なりますというと、語弊を生みそうですが、これは男性との身体的な違いもありますが、この国が抱える文化というか、ジェンダーギャップがあります。女性にとって過ごしやすい社会ではないことがあると思います。
先ほど、研修は勤務時間外や休日のものもあるといいました。受けたい研修があっても、子育て中の場合は諦めることケースもあるかもしれません。性別は関係ないといえそうですが、私の実感としては、女性の方か参加しにくさを抱えているように感じます。
もし、我が子が熱を出した場合、母親か父親、どちらが迎えにいきますか?
子どもの授業参観や懇談会だったら、母親と父親、どちらの方が参加率が高いですか?
私の実感としては、圧倒的に女性の方が多いです。それほど、子育て=女性というのが、まだまだ染み付いている社会ですし、保育者の学びの機会をおいても、女性は本人の意思とは反しての参加しにくさがあるのでないでしょうか。
そんなことを書きながら、私も甘えてしまっていることに反省しています。
・余裕、余白がない
そして、最後に保育者に“余裕、余白がない”です。
保育者はその勤務時間のほとんどが子どもと関わる時間です。しかし、それ以外にやることが山のようにあります。
その日の保育日誌、保護者への連絡帳、その日のお便りづくり、保育の振り返り、季節の取り組み・行事・懇談会などの準備、会議、安全点検、その日の保育の片付け、翌日の保育の準備と確認、保育室やトイレなど全ての部屋の掃除など。これはほぼ毎日するものです。
感染症が流行っている場合は、感染症対策、流行っている感染症の周知、感染防止の掃除がここに入ります。子どもが急に熱が出たり、嘔吐、またはケガなどした場合は、病院と保護者への連絡、引率する保育者などの段取りの確認などが入る時もあります。子どもの人数が多い保育現場であればより対応も多くなるのではないでしょうか。
保護者から意見やクレームがあった場合は、急遽、面談や対応の確認をする時間が必要となることもあります。送迎の駐車のことやご近所のこと、小学校や療育機関との連携などなど、予定していることも想定外のことも起こる、それが保育現場です。今、思いついたのがこれだけで、絵本や教材の修理など、出したらキリがありません。
勤務時間のほとんどが子どもと関わる時間なのに、これだけの“やらなければならない”ことがあるのです。では、どの時間にやるのか? 休憩時間や勤務時間外に残ってやることもあります。勤務後に家に持ち帰ってやる人もいるでしょう。
こんな状態で、どう“保育を育てる”のでしょう。
私は保育を育てるのは、保育者が育つ研修もそうですが、その日の“子どもの姿”や“保育”を振り返り、共有することが“保育を育てる”ことの根幹だと思っています。
けれど、これだけの業務があったら、その保育者同士の共有は後回しになりますし、研修なんて受ける余裕も、余白もないのです。これでは保育が育つはずもないのです。
ここまでが 保育が育たない理由の一つ目、保育を育てにくい構造 です
次回は
その②変わらなくてもできてしまう保育(過去のままやればいい。子どもは訴えているけれど、保育者はクローズエンド。時代にも子どもにもあっているのか。)
です。次回もお付き合いいただければ幸いです。

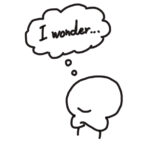
旅する保育者 地図屋のMy Wonder Journeyはコチラ🫱

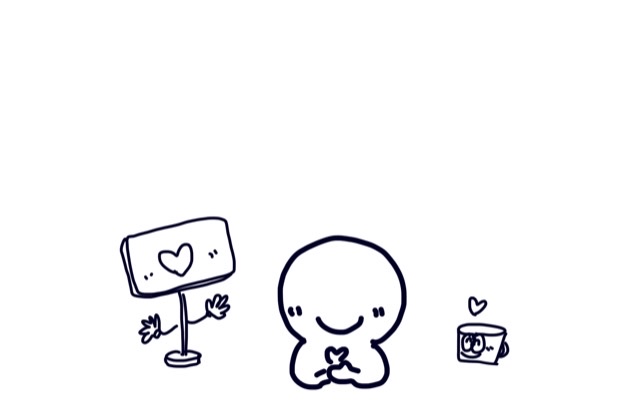
World Map 5の最近の購入もの
キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本
尊敬する猟師 千松信也さんの映画『僕は猟師になった』公式パンフレット





本日もご来店ありがとうございました。
毎日が皆様にとって素敵な日になりますように
それでは
Have a nice dream day.🎫✈️
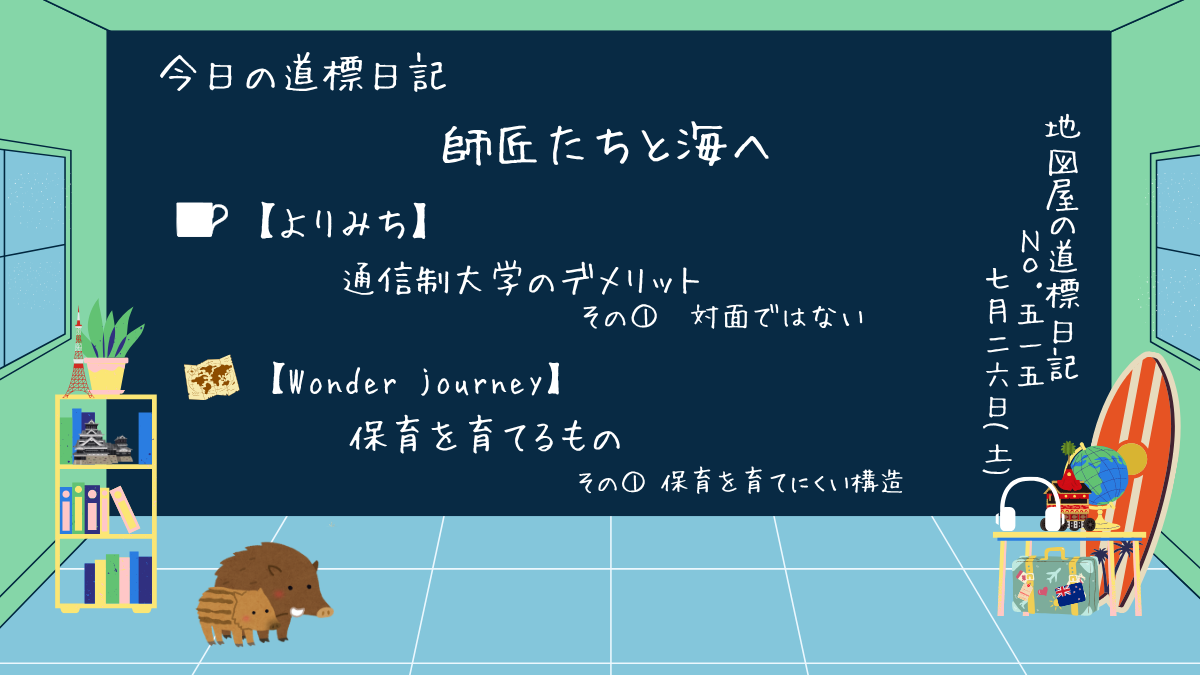
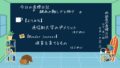
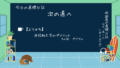
コメント