
こちらは旅する保育者としての私が、日々の保育や学びのなかで生まれた“不思議”“問い”をつづる場にしたいと思い始めました。常に問いとそれを探求する思いを持ち、保育者として成長し続けたいです。
今回は、【 保育を育てるもの 】です。
🗺️My Wonder journey 【 保育を育てるもの 】 はじめに
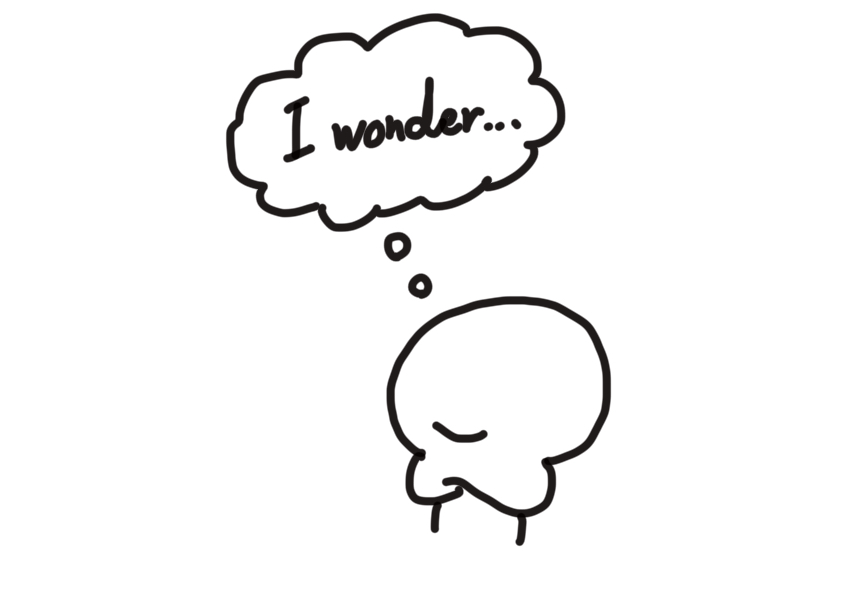
今回は保育への愚痴からの My Wonder です。笑
保育園や幼稚園、認定子ども園は、“子どもを育てる”場です。これは皆さんご承知の通りだと思いますが。
加えて、、というか、何かそんな言い回しにも私は違和感を感じるのですが、もう20年近く保育者として過ごしてきた私は、この場は、“人が育つ”場 だと強く実感しています。
保育園、幼稚園、認定子ども園など、就学前に子どもたちが過ごすこの場は、その子どもの保護者、そして、子どもに関わる保育者も育つ場だと思って、私は毎日、保育をしています。そこの“保育”に関わる全ての人が育つ場。それが保育だと考えています。
では、その“保育”を育てる人は誰なのでしょう。 それは保育者だと考えています。つまり、保育者自身が研鑽を続ければ、保育者の行動、言葉、目線、ふるまいが変わり、それらが子どもや仲間の保育者、保護者、さらには地域に伝わっていくと、保育がじわじわと変わっていく。これを私は、保育が育つことだと思っています。
しかし、保育を育てるはずの保育者が学ぶことしなければどうなるでしょう? 毎年同じ保育、同じ行事、同じ言葉かけをしているだけで日々の保育が過ぎていくのです。向き合う子どもも、保護者も、そして時代も違うのに、例年と同じような保育をする。これは、保育のズレを生み出すのではないでしょうか。
けれど、保育を育てることの難しさが現実にはあると思います。私が考える“なぜ保育者が育たたないのか”を今回のWonderをさせていただきます。3つあげるとすると、
その① 保育を育てにくい構造
その② 変わらなくてもできてしまう保育
その③ そもそも育つことをしない(変わらなくてもいい、就職したらこっちのもん社会)
以上の3つが現実に保育を貞に草へとつながっていると感じます。
それでは1つずつ綴っていきましょう。

その① 保育を育てにくい構造
まず1つ目が、そもそも保育現場というのは“保育を育てにくい構造”をしていることです。(これは私の経験をもとにしていますので、当てはまらない保育現場もあるかもしれません。ご了承ください。)
・研修を複数人で受ける保障がされていない

私の保育園では、研修があります。研修には都道府県、市町村、所属団体、大学、研究団体、企業など様々な研修があり、新人、中堅、管理職、研究生など、その人に合わせた研修を用意する場合もあります。
その研修は勤務時間内・勤務時間外で行われるものがあります。また、土日や祝日に行われるものもあります。
園から研修を受けるように言われているのなら、まだ良い方かもしれません。それが園の保育を育てるためのものならですが。
勤務時間内の研修であると、保育現場から保育者が出ることになります。現場が欠ける分はフリーなどの職員が入りますが、必ずしも体制の保障があるわけではありません。そんな余裕のある現場は少ないのではないでしょうか。また、研修に出せたとしても1〜2人ぐらいのもので、複数で受けることはほとんどできません。大体、1人で研修を受けて、報告書を書いて、会議などでちょっと共有しておしまいではないでしょうか。このフィードバックの薄い構造が“保育の育ちにくさ”につながっていると感じます。
・女性が多い職場
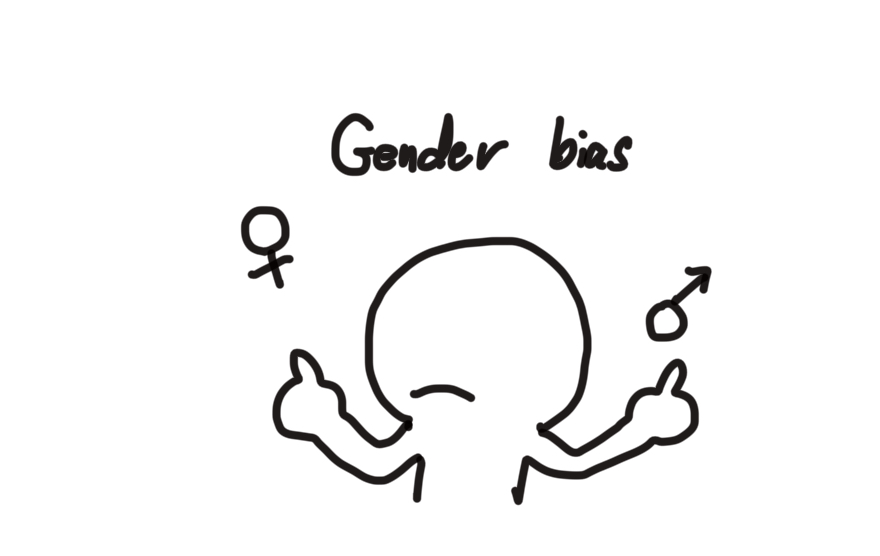
このパートは、言葉を選ぶところもあるのですが、綴っていきます。
保育現場は男性保育者も増えてきたとはいえ、そのほとんどが女性保育者です。
女性の場合、産休があったり、子どもが生まれた場合、我が子・家庭中心の生活になります。なりますというと、語弊を生みそうですが、これは男性との身体的な違いもありますが、この国が抱える文化というか、ジェンダーギャップがあります。女性にとって過ごしやすい社会ではないことがあると思います。
先ほど、研修は勤務時間外や休日のものもあるといいました。受けたい研修があっても、子育て中の場合は諦めることケースもあるかもしれません。性別は関係ないといえそうですが、私の実感としては、女性の方か参加しにくさを抱えているように感じます。
もし、我が子が熱を出した場合、母親か父親、どちらが迎えにいきますか?
子どもの授業参観や懇談会だったら、母親と父親、どちらの方が参加率が高いですか?
子育て中の私の実感としては、圧倒的に女性の方が多いです。それほど、子育て=女性というのが、まだまだ染み付いている社会ですし、保育者の学びの機会をおいても、女性は本人の意思とは反しての参加しにくさがあるのでないでしょうか。
そんなことを書きながら、私もパートナーに甘えてしまっているところが多いことに反省しています。
・余裕、余白がない
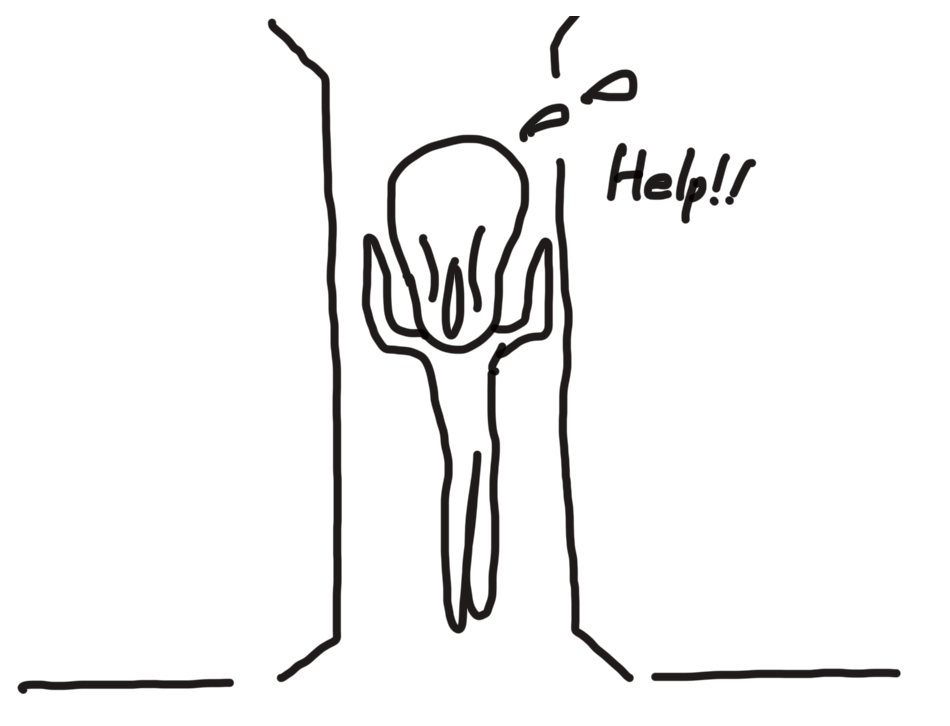
そして、最後に保育者に“余裕、余白がない”です。
保育者はその勤務時間のほとんどが子どもと関わる時間です。しかし、それ以外にやることが山のようにあります。
その日の保育日誌、保護者への連絡帳、その日のお便りづくり、保育の振り返り、季節の取り組み・行事・懇談会などの準備、会議、安全点検、その日の保育の片付け、翌日の保育の準備と確認、保育室やトイレなど全ての部屋の掃除など。これはほぼ毎日するものです。
感染症が流行っている場合は、感染症対策、流行っている感染症の周知、感染防止の掃除がここに入ります。子どもが急に熱が出たり、嘔吐、またはケガなどした場合は、病院と保護者への連絡、引率する保育者などの段取りの確認などが入る時もあります。子どもの人数が多い保育現場であれば、よりその対応も多くなるのではないでしょうか。保護者から意見やクレームがあった場合は、急遽、面談や対応の確認をする時間が必要となることもあります。送迎の駐車のことやご近所のこと、小学校や療育機関との連携などなど。
予定していることも想定外のことも起こる、それが保育現場です。今、思いついたのがこれだけであって、絵本や教材の修理など、出したらキリがありません。
勤務時間のほとんどが子どもと関わる時間なのに、これだけの“やらなければならない”ことがあるのです。では、どの時間にやるのか? 休憩時間や勤務時間外に残ってやることもあります。勤務後に家に持ち帰ってやる人もいるでしょう。
こんな状態で、どう“保育を育てる”のでしょう。
私は保育を育てるのは、保育者が育つ研修もそうですが、その日の“子どもの姿”や“保育”を振り返り、共有することが“保育を育てる”ことの根幹だと思っています。
けれど、これだけの業務があったら、その保育者同士の共有は後回しになりますし、研修なんて受ける余裕も、余白もないのです。これでは保育が育つはずもないのです。
以上が 保育が育たない理由の一つ目、保育を育てにくい構造 です
その② 育てなくてもできてしまう保育
次は、“育てなくてもできてしまう”保育についてです。
これは、保育者が別に変わらなくても、そのままの保育をやっていたら問題が起こらない(みえない)といったことです。ちょっと乱暴な言い方になりますが。
・過去と同じことをやっていれば良い

歴史のある保育現場であると、一年の流れが大体決まっています。七夕やクリスマス、節分などの季節の行事や、運動会や生活発表会などの園行事とよばれるものがあります。
職員同士で話し合い、今年の行事・取り組みについての会議をしますが、どこか“例年と同じことをやっておけばいい”という雰囲気があります。
園の行事だけでなく、保育もですが、つくられた・やり始めた時は、その時の保育者や子どもの願いが込められているものだと思っています。「子どもにこんなことをさせてあげたい」「こうしたら目の前の子どもたちにそぐっているのではないか」など。それはとても大切なことであり、その時の子どもたちと保育者とのが考え合った“最善”のかたちだったのだと思います。
しかし、月日が経つと、そのかたちは残りますが、願いは薄れていきます。「去年もやってよかったから」と、大人(保育者や保護者)の中だけで“美化”されていき、「じゃあ今年もやろう」となります。これが“過去と同じことをやっていれば良い”という保育が育たない原因の一つとなっていきます。
本当に“今”目の前にいる子ども達への“最善”なのでしょうか。例年と同じことをするにしても、“願い”を深掘りすることをおざなりにしてはいけないと思います。
これは行事だけでなく、その園の環境が生むものもあります。それは保育のかたち(年齢構成、子どもの人数、職員の人数、規模、部屋数、園庭や給食室の有無、園がある土地の風土など)によって違ってきます。ルールであったり、導線、また、暗黙の了解の部分があるかもしれません。
それらが保育の“常識”としてあると、なかなか変えづらいものがあります。
“常識は思考停止”ということばがありますが、考えなくても良いのが果たして本当に子どものためなのでしょうか。
・文化が育てているものに気づくことも大切

しかし、“変わればいい”というわけでありません。その園の保育が積み上げてきた“文化”は子どもにとって財産でもあります。
最近読んでいる本📕『人はいかに学ぶのか』では
「文化の与える制約的条件のおかげで、人びとは容易かつ速やかに学ぶことができる」
と、あります。
これを、今回のWonderに合わせて私的に解釈をすると、
“その園の積み上げてきた文化は、知らず知らずのうちに子どもにとって最善の機会を与えている”ともいえるということです。歴史とともに積み上げてきた人間関係、地域との交流などの社会的資本(人と人との関係を資本として捉える考え方)も、その園の歴史や文化に当てはまるかもしれません。
園の保育を育てることために変化を促すことも大切ですが、その園の気づかない・当たり前になっている“文化”の中にある“子どもへの最善”を失わないようには気をつけなければならない、と、この本と出会って再考したことでした。その逆も然りですが。
その③ 育つことをしない
今回のWonder“保育を育てるもの”の最終回です。最後は、そもそも“育つことをしない”です。
保育を育てる保育者が“育つ”こととしないのには様々な原因があると思います。これは決して保育者だけの責任ではないと考えます。

1つは、“就職してしまえばこっちのもん”です。これは保育士という仕事だけではなく、日本の働き方の構造、いや、学びの構造にあると思います。
就職するまでは、学校などで必死に勉強するのですが、就職してしまうと“必要最低限の勉強”しかしなくなります。
保育現場で言うと、必要最低限の勉強とは、勤務時間内の勉強または研修のみです。勉強が勤務時間内だけというのを、悪いといっているのではありません。仕事以外は自分の時間。しっかり休み、余暇を楽しむことで、英気が養なわれることは、仕事への活力にもなります。仕事とプライベートとどちらの時間も、全ての自分の時間が充実してこそ豊かな人生です。それはどちらだけが良いというものではなく、人によって違いますし、またその時々で変わるものです。
しかし、そのバランスほど難しいのも実際あるのではないでしょうか。日本はまだまだ働きすぎだと思いますし、保育や教育現場でも働く人の多くは“残業”が当たり前になっています。少し前には過労死、そして、最近であれば、定額制働かせ放題などの問題がありますね。“残業”というものがまだまだ当たり前の感覚としてあるのが現状ではないでしょうか。
でも、全く改善されていないわけではありません。教育現場では働き方改革として、教員の働き方、部活動など課外活動への取り組み方も見直されるようになってきています。教科担任制やチーム担任制など、教員の負担を軽くするための取り組みも進んできています。
しかし、今の現場の先生に聞くと、また新たな課題が生まれてきそうではあります。残業が良いわけではないですが、これまでは残業の中で行われてきた教員同士のディスカッションやその日の保育や授業のフィードバック、自主的な研修なども、“やりづらくなった”と。私自身も、そして他の保育現場、教育現場でも同じような声を聞きます。働き方改革ということもあって、「一緒に勉強しようぜ!」とは言いづらい現状があります
残業が良いとはいいませんが、残業で培われていた自己研鑽の機会がなくなった分、保育や教育が育たちにくくなったと考えます。今は、残業で自己研鑽をしていた世代がいますが、自己研鑽の機会がないのが当然になったら、“育つことをしない”のが当たり前になってくるかもしれませんね。もうすでにそうかもしれません。それは本当にワークアンドライフバランスといえるものでしょうか。
終わりに・・・
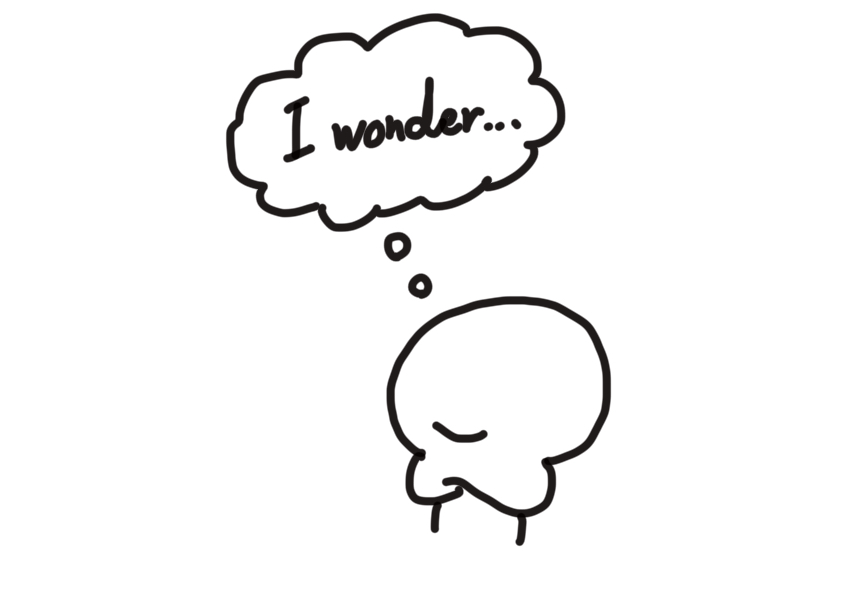
今回の Wonder Journey は、“保育を育てるもの”を
1、保育を育てにくい構造
2、育てなくてもできてしまう保育
3、育つことをしない
の3つに分けて綴らせていただきました。
私は、保育・教育現場に携わるもの自己成長してこそ、その専門性を磨いてこそ、“保育・教育は育つ”と考えています。しかし、私自身、今はそれを実感できていません。これは私だけが感じているものではなく、多くの“子どもを育てる場”の課題となっているのではないでしょうか。
綴っておいてあれですが、書きながら自分でもっと考察しなければならない課題だと感じました。まだまだ考えることが多いWonderだったと思っています。残すかどうか悩みましたが、“今の自分”の問いや実力としても残しておこうと思いました。今回深掘りできなかったWonderは引き続き自身の課題にしていきます。
そして、保育を育つことによって、日本の、いや、世界中の、保育教育が善くなり続けることを願っております。
私も最善を尽くします!
以上、地図屋でした。 では また👋





本日もご来店ありがとうございました。
毎日が皆様にとって素敵な日になりますように
それでは
Have a nice dream day.🎫✈️
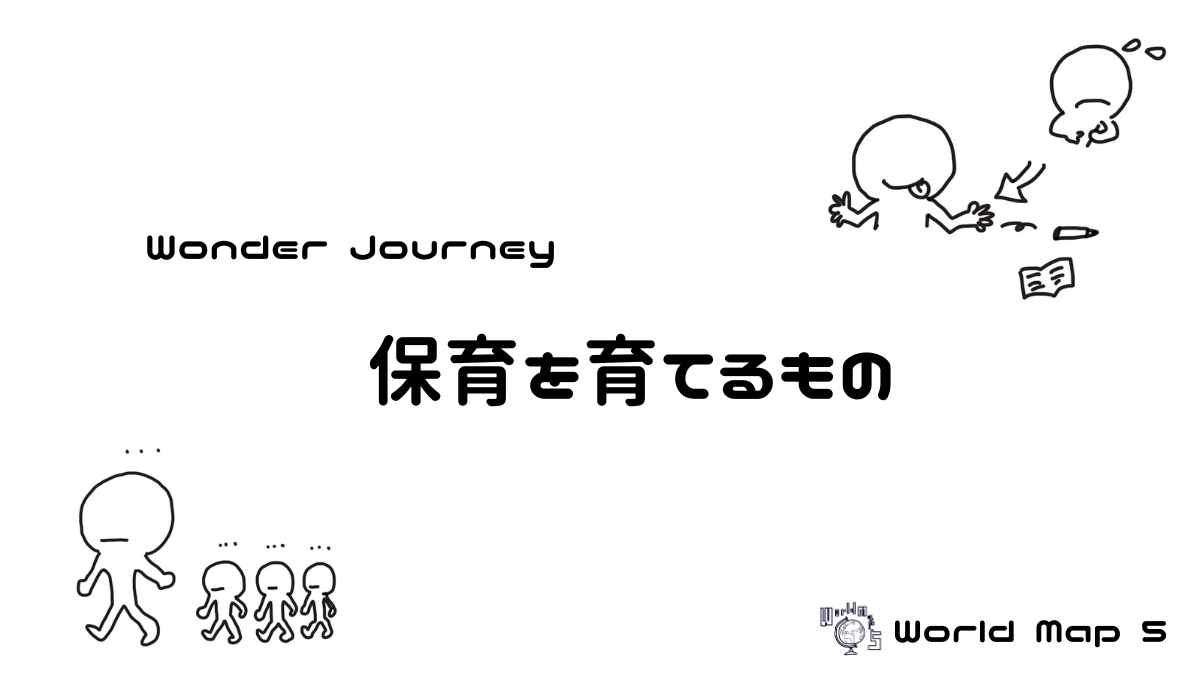
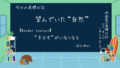
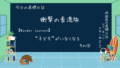
コメント