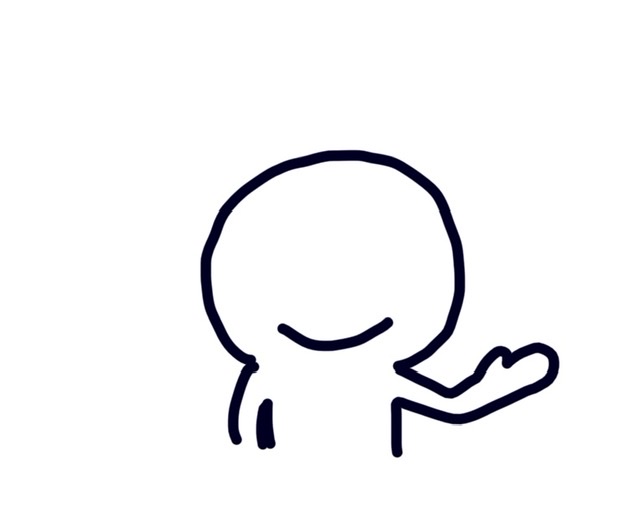
いらっしゃいませ 地図屋でございます。
本日は2025年4月20日(日)道標日記No.504です。 ご来店ありがとうございます。
新年度にはいり、半月が経ちました。皆さまはいかがお過ごしでしょうか😌
私はというと、我が子が中学生になり、“生活”が変わってきたことを感じています。学童に通わなくなり、習い事も終わり、付き合う友達も代わり、そんな我が子の“ふるまい”の変化に合わせて“家の流れ”が変化しています。
私自身も、キャリアブレイクからフルタイムである8時間になったことで“ふるまい”が変わました。帰ってくる時間、疲れ方、人との関わり、夢活への取り組み方、など。今はその“変化”に慣れていこうとしているところです。
皆さまも、変化に合わせてそのふるまいを合わせている時ではないでしょうか。そんな時は、どこかで気を張って、気づかぬ疲れも溜まっていることでしょう。新しいふるまいを身につけたころにゴールデンウィークがきて、リセットされるのも毎年のこと😅年度はじめが“2回”くると思ってボチボチやっていきましょう😌
暑くなる日もあれば朝晩は冷えたりと体調を崩しやすい時期です。どうぞ皆さまもご自愛ください☕️
さて 今回の道標日記は
👂耳勉強 【 すべては「好き嫌い」から始まる 仕事を自由にする思考法 】
🗺️My Wonder journey 【 保育の中のウソっぽさ ① 】
を紹介させていただいております。
私の夢への旅が、皆さまのお手伝いになれば幸いです。
夢への地図を描くお店 World Map 5 🗺
どうぞ ゆっくりしていってくださいね😌
👂耳勉強 【 すべては「好き嫌い」から始まる 仕事を自由にする思考法 】

👂今日の耳勉強はフェルミ漫画大学さんの
【 すべては「好き嫌い」から始まる 仕事を自由にする思考法 】
最も学んだこと💮
・プロになるなら好きが必要
好きなことは長時間継続してやり続けられる。結果的に他の人にはできない特殊能力を身につけることができる。
例えば
アリが好きな人は他人から褒められなくても結果が出なくても、毎日ワクワクしながら自発的にアリについて調べられる。それはシンプルに好きだからである。
そうした日々を数年間ずっと続けているうちに、いつの間にか他の人にはできないことができるようになる。要は『好きこそものの上手なれ』ということである。
しかし、アリが好きじゃない人にとって毎日アリについて調べることは苦痛であり、“努力”が必要になる。それでも結果が出たり、周りが褒めてくれれば努力を続けられるかもしれないが、結果が出なくなったり、すぐにやめてしまうのは、好きではないからである。これだと、数年間努力しても他人と違う特殊能力を手にすることができない。
そのため著者は「努力しなきゃ」と思った時点でそもそも向いてないし、他との違いをつくるほど極めることができないと指摘している。
仕事に好き嫌いを持ち込まず、お金を稼ぐことを目的にするのであれば、ただ言われたことをやればよい。そうすれば生活はできるが、替えはいくらでも利く存在になる。
他の人ができないことを1つでもできると、替えが利かない存在になるためものすごい価値が生まれる。そのためにはシンプルに自分の好きなことを突き詰める必要がある。
✅「その業界でプロになりたいのなら仕事が好きである必要がある」
・好き嫌いを言語化する
最初の夢はだいたい叶わないことが多い。向いていないことがわかったのなら、自分の好きな要素を導き出して軌道修正していく。
まず、自分が誰に何を言われるでもなく気づいたらやっている好きなことや嫌いなことについて、『なんで好きなんだろう?』『なんで嫌いなんだろう?』と問いを立てて自分なりの答えを導き出す。
ポイントは、自分の好き嫌いの要素をちゃんと言語化がするということである。人は言葉でしか考えられないようにできているからである。好き嫌いを言語化しておくことで、自分の好き嫌いを生活や仕事の選択に活かすことができる。これは仕事だけではなく、人生すべてに活用できる。
世間の物差しよりも、絶対に外せないのが自分の好き嫌いのポイントです。
高価なものより使いやすいもの。派手なものよりシンプルなもの。デジタルよりアナログ、など。
このように無意識に感じる自分の好き嫌いを小さく分解しておくと、就職だけじゃなく他のことでも自分の満足できる選択をしやすくなる。
✅「自分の好き嫌いを小さく分解して言語化する」
・さっさと行動する
何事もやってみないと好きか嫌いかわからないし、予想と現実とはまるで違うことが多い。Youtubeを実際にやってみても、想像と違って嫌いだったり、伸びると思ったのに伸びないことも多い。ゲームの新作も絶対おもしろいと思ってやってみても、実際にやってみると意外とつまらなかったということもある。
この本には「10時間の想像よりも、1分の実体験が大事」だと書かれている。そのため著者は、未知のことついてはあれこれ考えずに「ま、とりあえずやってみるか」という姿勢で生活している。
想像も大切だが、あくまでそれは経験した後の想像に限る。先に経験がないと、いい想像はできない。
✅「想像するのではなくさっさと経験する」
・好きなことをやるメリット
好きなことをやっていることで得られるメリット
①「結果はどうであれ、毎日やっていることがご褒美になる」
好きなことは結果がどうであれ、ただやっているだけで時間を忘れて夢中になれる。
文章が書くことが好きな人は、仮に、作った本が売れなくても「別にいいや」と思える。
阪神ファンも勝とうが負けようが応援している時点で楽しい。
もちろん結果が出た方が楽しいが、好きなことは仮に結果が出なくてもその過程を楽しむことができる。一方、結果がでないと続けたくないのなら、それはそれほど好きじゃないのかもしれない。
✅「好きなことをやっていると結果はどうあれ、毎日やっていること自体がご褒美になる」
②相手の好きも尊重できるようになる
自分が好きなことをやっていると相手の好きも尊重できるようになる。逆に、自分が嫌なことをやらされていると、相手にも嫌なことを強要したくなる。
例えば、自分が好きなカレーを食べている場合、相手がチャーハンを食べていても特に嫌な気分にはならない。一方、自分が好きでもない冷やし中華を強制的に食べさせられている場合、相手がチャーハンを食べていると、自分が我慢しているのに好き勝手やっている人に腹が立つし、「ズルい」と感じてしまう。
仕事も同じで、自分が好きな仕事をしていると他人が好きなことも許容できるが、自分が嫌いな仕事をさせられていると他人にも嫌なことを我慢させてやらせたくなってしまう。
そういう意味でも、1回きりの人生、自分の好きなこと、少なくとも嫌いじゃないを仕事にできるとよい。
✅「好きでやっていると相手の好きも尊重できる」

👂今日の耳勉強を振り返って…
久しぶりの耳勉強になりました😌
私は熱中するような“好き”と言えるものがなく、周りの人の“好き”を聞くと羨ましく思う時があります。子どもの時はありましたが、大きくなるにつれ、好きなようで実は“夢中にさせられている”ような感覚があり、本心ではないから冷めてしまうのでしょうね。どこか完璧主義なところや、人と比べて劣っていると思うと手を出せないところが、自分のクセでもあるということに大人になって気づきました。
“自分の好きがあると相手の好きも尊重できるようになる”とありますが、これは子どもも同じだと感じました。保育の中の子どもたちも、自分の好きがあるからこそ、それを土台に自分を広げています。それは遊びであったり、友達であったり、大人であったり。その土台があることが、世界を広げ、他者を認めることにもつながっています。
子どもにとっても“好き”が尊重される、尊重してあげたいと思う地図屋でした。
フェルミ漫画大学さん、楠 健さん 学ばさせていただきました😌👂

👂今日の耳勉強で紹介された書籍はコチラ🫱 📙
🗺️My Wonder journey 【 保育の中のウソっぽさ ① 】

こちらは旅する保育者としての私が、日々の保育や学びのなかで生まれた“不思議”“問い”をつづる場にしたいと思い始めました。常に問いとそれを探求する思いを持ち、保育者として成長し続けたいです。
今回は、【 保育の中のウソっぽさ 】です。
耳勉強が長くなったので、今回のwonderは序論的にしようと思います、、、。
保育の中のウソっぽさ
これは10年以上保育をしてきた私が感じ始めたことです。「あー、ウソっぽいなぁ」と思うことが時々あるのです。それは保育者の子どもや他の大人への関わりから感じるのです。
保育の中で、、いうや家庭の中でもあると思いますが、子どもが“大人”にとってやってほしいこと(成果、都合の良い行動)をした時、「うわぁ、○○ちゃんじょうずだねー!」と声をかける時があります。
この言葉が、感情がこもってなく、薄っぺらく感じるのです。
大人の思っている世界、大人の正しい世界に“当てはまる”ことをした時に、このような言葉がかけられるのです。ここに大人の本心はないように感じます。(ほんとうにそう思ってる?)と、へそ曲がりな私は思ってしまうのです。
そこには大人が抱えている、子どもを“社会化”させないといけない、というプレッシャーや責任があるのではないでしょうか。
子どもは純粋で発達途上なので、そのことばをかけられた時、(この行動、結果が大人に喜ばれんるんだ)(じゃあ大人のために引き続きコレをやろう)とするのではないでしょうか。これは大人のためではないか?でも、将来的には子どもが生き抜くための“すべ?”“社会性?”になるのなら子どものためなのか、、、今の私にはピンときていないところです。
でも反対に、子どもが大人にとって困った行動を取ると、そこにはすごく大人の感情がのっているのですよね。大人にとって理解できないことであったり、誰かに迷惑がかかるようなことであったり、都合の悪いことだったり。そこにはウソではない本物の感情がのっています。悲しいものですが。
子どもが褒められたい時は“ウソ”にふれ、怒られる時には“ほんもの”にふれている。
ここが私の今回のwonderです。この続きは次回の🗺️wonderで


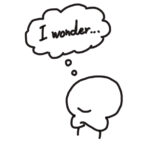
旅する保育者 地図屋のMy Wonder Journeyはコチラ🫱


本日もご来店ありがとうございました。
毎日が皆様にとって素敵な日になりますように
それでは
Have a nice dream day.🎫✈️
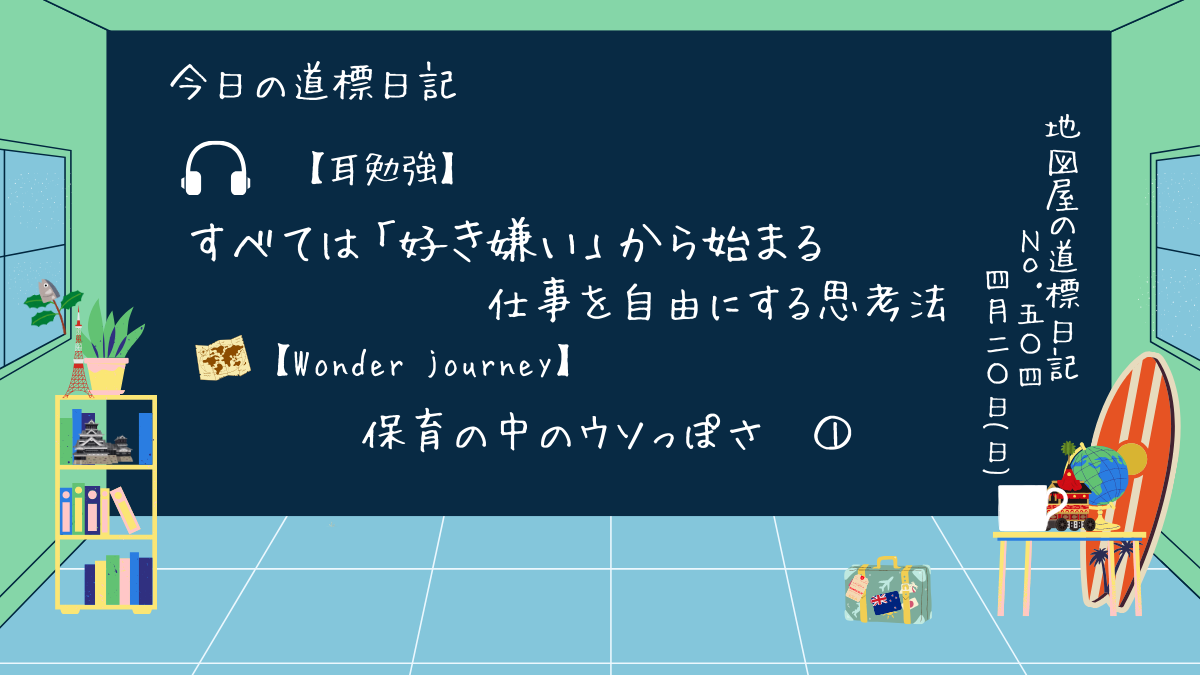

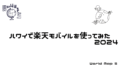
コメント