
始まりました🗺️My Wonder journeyのコーナーです。
こちらは旅する保育者としての私が、日々の保育や学びのなかで生まれた“不思議”“問い”をつづる場です。常に、問いと探求する思いを持ち、保育者として成長し続けたいと思っております。
今回のMy Wonderは、ある園を見学させてもらった時に生まれた3つのWonderなります。この3つはどこの園にもあることなのではないかと思います。
私の中から生まれたWonderが、保育をより善くするための道標になれば幸いです。
それではまいりましょう🫱 🪧
今の保育への問い
旅する保育者である私は、ありがたいことに色々な園・学校を見る機会がいただいております。○○府の園に見学に行ってきました。そちらの園は歴史もあり、広く事業展開もしており、コアな保護者からも人気のある園でした。園長先生が情熱的で勉強家でもあり、その理念を職員の方々も持って、保育に取り組んでいるように感じました。
今回、見学させてもらったなかで生まれた“Wonder(不思議・問い)”を3つあげるとすると、
①、保育の中の“男女”?
②、質の高い保育には“+α”が必要?
③、勉強熱心はトップダウン?
です。
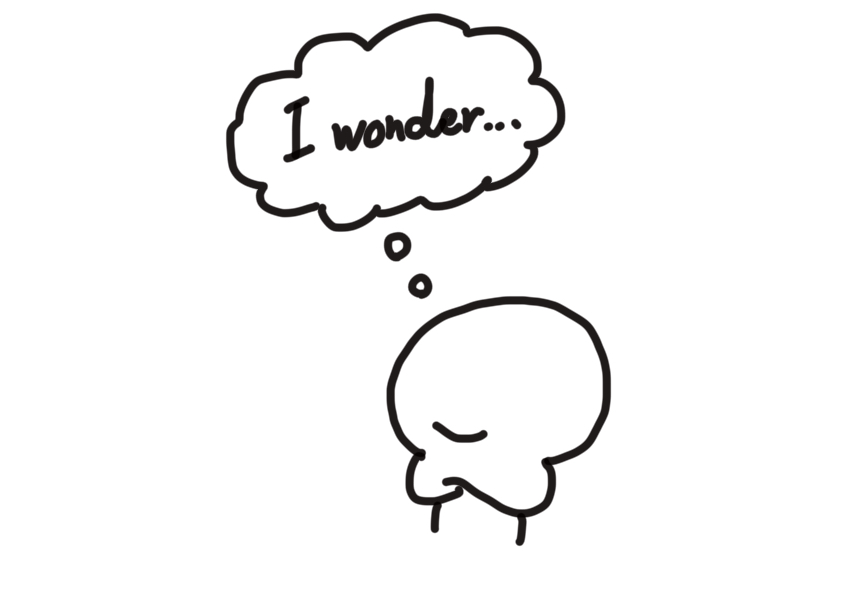
私は園の保育を否定したいわけではありません。保育は、人、もの、場所でかたちが変わるものであり、一つとして同じ保育のかたちはありません。当然ですよね。ちがうからこそ、“問い”が生まれるのです。その問いを深めることで私自身の保育を深めるともに、これが“保育をより善くするための道標”になれば良いと考えています。なのであたたかくお付き合いいただければ幸いです😌
1、保育の中の“男女”?
先日行った園は、年齢別での活動や行事で“これ”というものは決めておらず、子どもとのやりとりからクリエイティブな活動を展開しています。完成や正解がなく、常に過程であり、探究し続けることを大切にしており、子どもが伸び伸びと表現する姿がありました。このなかの“自由”には、どの子もが居やすい雰囲気があり、多様性の認め合いがあると感じました。
だからこそ、Wonderがありました。
私たちが来園して、理事長先生(男性)と園長先生(男性)と話をするときに主幹(主任・副園長)の女性の方が“お茶”を出してくれたのです。ここに懐かしさというか保育とのギャップを感じたのです。率直に感じたのが“女性がお茶を出す”がまだある、ということです。あまりにも自然に、言葉もなく、お茶が出てきたことに“今”の私には違和感があったのです。
視察を終えての懇談で、“保育者の働きやすさ”のついて質問したときにも、違和感がありました。「女性はホルモンバランスの乱れがあるから、それが保育に影響でないように工夫している。そのような状態で保育をしてほしくないので」と。これはその空間にいるのが男性ばかりだったのでここだけの話のようにものに思えましたが、その“工夫”に私はこれまで出会ったことがなかったので、今回は自分にない見解として受け取ることにしました。私は自認する性が男性なので、もしかしたら自分の周りではその“工夫”がなされており、私がその“工夫”に気づかなかっただけかもしれません。気づいていることといえば、女性の生理で体調が優れない時などに、女性同士で声をかけ合ったり、配慮しあっている“工夫”なら感じたことがありますが。
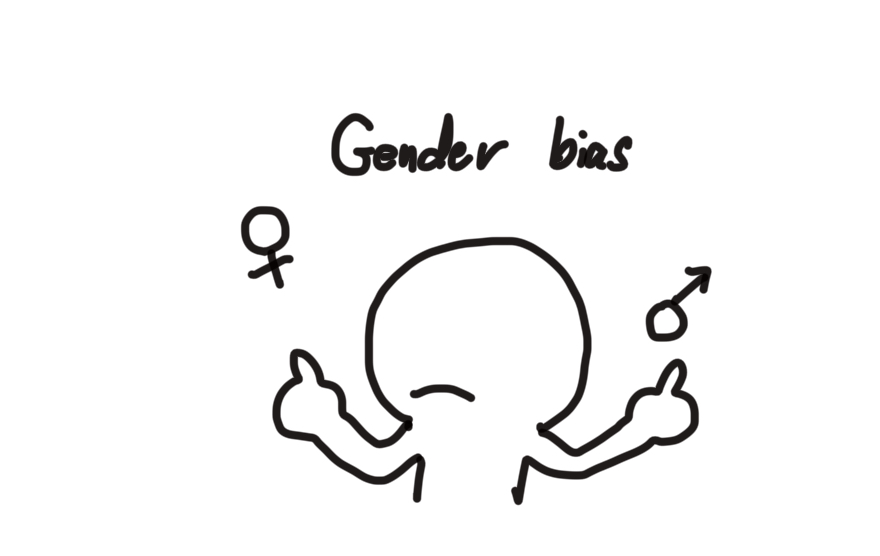
あと、生活発表会の練習の様子をみせてもらう機会があったのですが、そのなかでもwonderがありました。子どもとつくり合い、日々変わる遊びをどう工夫するか、表現するかを職員間で試行錯誤され、職員も得意性や専門性を活かし、伸び伸びと取り組んでいました。ただ、場面の切り替わりで「じゃあ次は女の子から!」で“wonder”が生まれました。私のこれまでの学びでは、“子どもはまだ性自認が確立しているわけではない。自身のペースで獲得していくものである”と考えています。男女の2つだけでもないと認識しています。その自分だったので迷いなく発せられた「女の子から!」に問いが生まれたのです。子どもの自主性を尊重している保育を見たからこそ問いが生まれたのでしょう。
今回の視察では、保育の中の“男女”を感じることができました。これは歴史・文化的背景もある根強さも感じられました。はじめてみる魅力的な保育であったからこそ、“意外”だったのだと思います。
2、質の高い保育には“+α”が必要?
2つめのWonder “質の高い保育には+αが必要?”ということです。
視察にいった園は、保育者がゴールを決めて子どもに提供するのではなく、毎日の子どもから生まれ変化し続ける“遊び”を大切にしていました。子どもは毎日の自分の発想や表現をしっかりと保育者受け止めてもらえることで、伸び伸びと、そして主体的に過ごしている姿がありました。これは本当に勉強になりました。
この、子どもの意欲的な活動が生まれるのは保育者の方々の努力があってこそです。毎日変わる子どもの“学び”“意欲”に応え続けているからだと思います。これは同じ保育者として本当に尊敬しております。けれどそこには+αの努力があるのではないでしょうか。
子どもの学びが毎日変化するということは、それに合わせた準備が必要になります。それは保育者の勤務時間外、つまり“残業”でまかなわれるのです。
子どもの学びに答えるためには、保育者の経験や態度が大きく関わってきます。自身を磨き続けた熟練の保育者ほど、その相互作用は大きなものになるでしょう。それは保育をし続けた者の“喜び”ともなるでしょう。しかし、まだその域にたどり着いていない者、つまりあまり保育経験のない保育者にとってはプレッシャーになるかもしれません。それは周りに言われたわけでなくても、大きな“かせ”になるかもしれません。「隣のクラスはすごく楽しそうなのに、自分のクラスは・・・」。だから、自分の力不足をカバーするために“残業”をする。
子どもに応えようと保育者は一生懸命になるでしょう。それはプライベートを削るほどに。努力すれば、子どもと共に大きな喜びを得られるかもしれません。得られたとしても、その先も酷使し続ける自分でいられるでしょうか。

園長先生のお話を聞いた時、「職員に無理をしろと言っているわけでないのです。正解を出しなさいと言っているわけでもない。ただ、(うちの園の保育に)合う人は合うんですけどね」という言葉がありました。私も保育現場にいるので、その言葉が全くわからないわけではありません。けれど、保育者が自分に無理をさせてまで、そして、保育という立場のものが“人を選ぶ”のもどこか違うような気がしています。
これは視察にいった園だからの“問い”ではないと思います。+αをやり続けることの限界にきた時、園の期待に応えられないと感じた時、保育者は“自分には力がない”といい、辞めていくのではないでしょうか。
これまでの保育に根付いてきた“課題”を感じた地図屋です。
3、勉強熱心はトップダウン?
では最後のWonderです。
今見学をさせてもらった園の理事長先生は熱意を持った方で、子どもにも愛情あふれ、そして勉強熱心な方でした。その園長先生の熱意があるからこそ、この園の保育が生まれたのだと感じました。
そこには、他者が入る隙もないぐらいの“もの”がありました。なんと言ったら良いのか、うまく文にできませんが、ここでは思ったままに文章にします。残しておくことで後で文章化できると思いますので。
保育に勉強熱心な方がいるのは、保育の質の向上につながるので間違いなく良いことだと思います。けれど、私の経験からして、保育業務の中で勉強ができる人は限られてくると思います。毎日、保育をし、業務をするだけでも“人”も“時間”も足りないのです。時差勤務もありますし、子育て中の人もいますし、2つ目のWonderのでも述べたように、残業していることも多いのではないでしょうか。今の保育の状況では、保育のための“勉強”ができる人は限られているのではないかと思います。
勉強している人はその園の中で、その学びや実践を広げていくでしょう。他の保育者からも一目置かれるようになり、より自分の学びや実践に磨きがかかるようになるのではないでしょうか。
次第にその人のやり方が認められるように、そこに“正しさ”が生まれてきます。理論的な実践に、誰からも尊敬され、指示を仰がれるようになるでしょう。しかし、そのあとは、誰も物申せなくなるのではないでしょうか。ここに今回のWonderである“勉強熱心はトップダウン?”があるのです。

その人は、誰にも問われることがなくなり、自身の正しさが加速し、下手をすると“間違い”に気づくことがなくなるのではないでしょうか。すると、自身の心地よい保育をつくるだけに陥ってしまうかもしれません。ここには戻れなくなる危険もあります。それが園の文化として根強くなってしまうこともあるのではないでしょうか。
こうならないためにはどうすれば良いのでしょうか。職員間の心理的安全性による日々のディスカッション、学ぶものの謙虚さ、平等な学びの機会の構築、働き方の改善など浮かびます。
私は“余”が必要だと思います。詰め込みすぎない“余白”、子どもと保育者と保護者とが相互に語り合える“余談”、追われることのない働きやすい、そして生きやすい“余裕” が保育のなかにも、子どもの生活にも、大人の生活にも必要なのだと考えます。
これは保育の中だけの課題ではないのです。私たちの社会の課題だと思うのです。単純にそれらの“余”を増やしても本当の保育の質の向上にはつながらないでしょう。今はあまりにも社会の中に“余”がないのではないでしょうか。
この“余”が今後の私の研究の課題にもなってくるでしょう。引き続き、問い続けていきます。

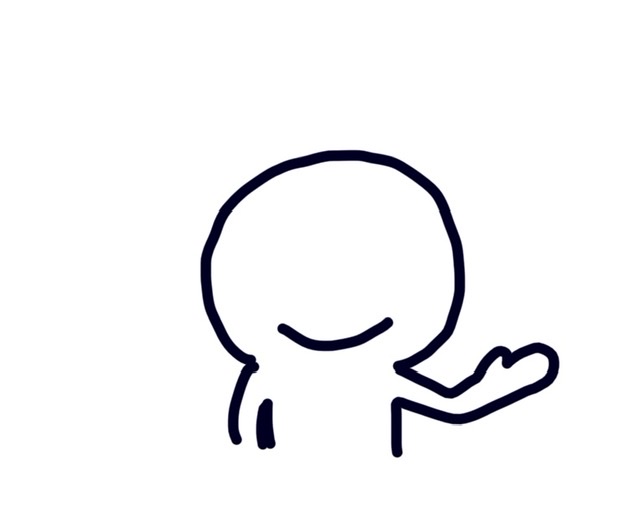
🗺️My Wonder journey いかがだったでしょうか?
これからも自分から生まれた保育の中のWonderをつづっていこうと思います。このように残すこと、自分の考えをアウトプットすることが今は大切だと考えています。これからこのコーナーがどのようになっていくか私にもわかりませんが、“より善い保育”のためになると信じて続けていきます。
これからも🗺️My Wonder journey をよろしくお願いします。


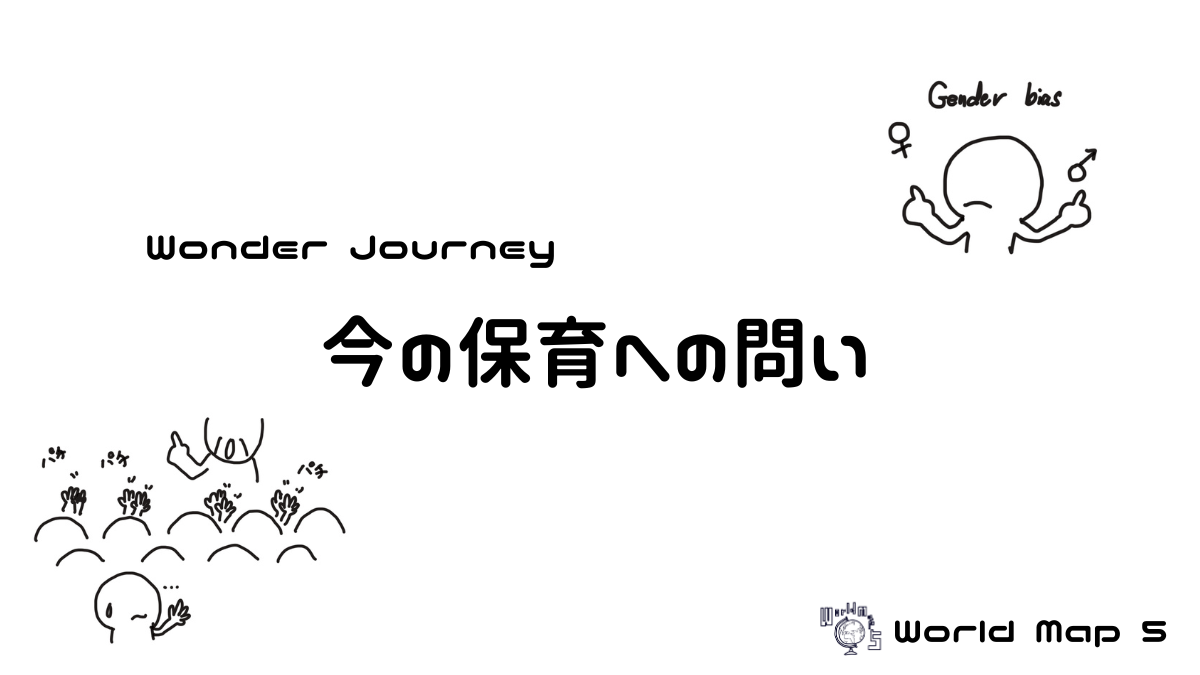

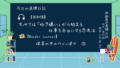
コメント