
こちらは旅する保育者としての私が、日々の保育や学びのなかで生まれた“不思議”“問い”をつづる場にしたいと思い始めました。常に問いとそれを探求する思いを持ち、保育者として成長し続けたいです。
今回は、【 なぜ“この道”を歩んでいるのか 】です。
☕️よりみち 【 なぜ“この道”を歩んでいるのか 】 はじめに
今回は“保育とは?”という私の問いの旅を振り返ります。
というのも、毎日、子どもと関わり、勉強をし、問いを持ち続けていますが、ふと、“なぜ、この道を歩んでいる6のだろう”と、わからなくなった自分がいたのです。
私は“保育がより善くなるように”と思い、正規職員をやめ、通信制大学に通い、海外の保育を目指し始めました。しかし、今は、その時の夢とはちょっと違う道を歩んでいます。全く違う道を歩んでいるわけではなく、目的地は同じなので、前ほど目的地が見えてはおらず、目の前に霧がかかっているようなところにいます。だから、“なぜこの道を歩んでいるのだろう”と迷っている自分がいるのだと思います。
そんな迷いの中にいる今の自分だからこそ、これまでの自分の旅を振り返り時なのだと思います。今回は私のここまでの旅 My Wonder Journey を綴らせていただきます。
次回からは、ここまでの私の旅で通過してきた“🪧立札”を順に綴っていきます。
🪧その1 自分の成長が止まった
🪧その2 ニュージーランドを目指す
🪧その3 道標人(みちしるべびと)出会う
🪧その4 研究者への道
🪧その5 今、必要な保育とは?
🪧その6 人として生きる 狩猟の道
です。
ここまでの旅を振り返ることで、目の前の霧が晴れるかもしれませんし、濃くなるかもしれません。歩みが速くなるかもしれませんし、立ち止まることになるかもしれません。しかし、綴ることが今後の自分の旅の糧になることを信じて書いていきます。これまでの私の旅の履歴を辿るこの日記を、あたたかく見守っていただけたら幸いです。
🪧その1 自分の成長が止まった
私は退職前まで、保育士として働き、副管理職も務めていました。この仕事が好きでずっと続けたいと思うほどでした。
しかし、保育士として過ごすうちに、自分の保育に疑問を持つようになりました。
・自分の都合の良い保育、子どものためではなく、自分のための保育をつくろうとしている
・専門性を振りかざして、子どもにも保護者にも上手くいいくるめるような言い回しや調子のよさ
・肩書きや学んでいるという権威性をもって、誰にも口出せないようになっていた。
・管理職というその席に居続けようとした。
そんなことを自分に思うようになったのです。
このままでは自分は成長しない。このように感じていた時期に、様々な巡り合わせとなる“機会”が訪れました。
それは
・保育先進国と言われるニュージーランドの保育者との出会い
・家庭の状況の変化(パートナーの働き方、我が子の生活、我が子との時間)
・コロナのおさまり
私はもともと“海外の保育”に憧れていました。様々な巡り合わせの中で、人生の転換期にいると感じ、もう一度、海外の保育にチャレンジすることを決意しました。ニュージーランドの保育へ飛び込たいと。
そのため、正規職を退職し、通信制大学に通い、仕事をパートにしたのです。
🪧その2 ニュージーランドを目指す
ニュージーランドで保育士として働きたい私には、2つの資格が必要でした。
1つ目が、大学の教育学部を卒業していること
2つ目が、IELTSでスコア7.0 の英語力
この2つになります。
そのために、まず、通信制大学の教育学部に入学しました。
私の当時の“甘い”計画では、通信制大学を最短の2年で卒業し、大学の勉強と共に、英語の勉強をしてIELTSの必要スコアも取得し、ニュージーランドで保育士として働くという計画でした。
この時の私は“自信”に満ち溢れていました。
仕事では活躍の場とポジションが与えられ、ポモドーロテクニックや自分磨きにも力を入れ、朝活や休憩時間も学習するほどの自分になれていたので、その計画を達成することができると思っていました。
しかし、この自信は退職&入学後に、どんどん薄れていきました。
自分の思っていた以上に、通信制大学の勉強に苦戦をしたのです。はじめの方は、通信課程の勉強のやり方に慣れていなかったのもあります。テキストの購入、レポートの提出、スクーリングの申し込み、最終試験の受け方。そして、生活のなかでの勉強時間の確保など。私の実感としては入学して2年経った頃に、ようやく“自分のもの”にできた、通信制大学というもに慣れたと感じました。
そんな状況だったので、英語の勉強は全く手をつけることができませんでした。それまでやっていた音読も、単語の暗記も、オンライン英会話もうやめて、通信制大学に専念することにしました。そして退職&入学して3年目の今の私に至っています。
なので、当初計画していたニュージーランドの地にはおらず、今も日本にいます😅
これには計画の甘さもあったのですが、退職&入学後に自分でも予想していなかった出来事があったのです。
それは
本当にニュージーランドに行けたことです。
🪧その③ ニュージーランドでの道標となる人たちとの出会い
私はこの時、「ニュージーランドの保育を見てみたい!」と口に出し続けていました。口にしていることは現実になるといいますが、それが本当になったのです。
ある研究会でニュージーランドの保育について研究されている方に偶然出会い、私がニュージーランドを目指していることを伝えると、「じゃあ、今度一緒に行きますか?」と言ってくれたのです。
これは、私の生きてきた中でもトップ3に入るほどのサプライズでした。その時は研究会そっちのけで興奮しっぱなしだったことを今でも覚えています。
・実際にニュージーランドの保育に触れる
夢のような機会を頂き、今自分ができる最善の準備を整えてニュージーランドに飛びました✈️
この旅では、保育施設だけでなく、小学校や大学への視察にも同行させていただきました。こんなにも早くニュージーランドの生の保育に触れることができたのは、本当に幸運だったと思います。
実際にニュージーランドの保育に触れて感じたことはたくさんあったのですが、私の未熟な頭と経験では得られるものに限界がありました。それでも見学はじめのうちに感じたことは、自分が思い描いていたほど魅力的な保育があるわけではなく、正直、「早く帰って、自分の保育がしたい」という思いがその時は浮かびました。
しかし、最後に訪れた保育施設で、まさしく自分がニュージーランドの保育に追い求めていたものがあったのです。それは感覚的でしたが、私はその園に足を踏み入れた時から、それまで訪れた園とは違う感覚があり、その園のアットホーム(この言葉さえ当てはまらないほどの)保育の魅力に惹かれました。
ここで私は改めて、ニュージーランドの保育を学びたい(というよりも、その園で保育を学びたい!)と、強く、そして具体的に夢のイメージを描くことができました。
・突きつけられた“厳しい現実”
なぜこのような見出しかというと、、、
ニュージーランドの保育を見るたびは楽しい、夢が叶った、と言えることばかりではありませんでした。正直、辛かったことも同じくらいありました。
一緒に同行した方々は、自分よりも保育を勉強し続け、研究し続け、その場にいることが“ふさわしい”人たちばかりでした。そして、ニュージーランドの憧れの保育の場にいた方々も、同じく、自分にとって雲の上のような人たちばかりでした。
私は、この人たちに出会えたことで、その人たちのような人になりたいと強く思いました。それとともに、今の自分では到底届かないという“現実”を突きつけられ、私のニュージーランドで保育をしたいという夢は、この旅ではるか彼方に行ってしまったような感覚がありました。
それでも、このことにこんなにも早く気づけたことはものすごく幸運なことだったと思います。このニュージーランドの旅は私の人生の宝物です。
🪧その④ 次、目指すものは?
ニュージーランドに行く目標が早くも叶ってしまった(現実を突きつけられた)私は、次の道がわからなくなりました。
🪧ニュージーランドに一緒に行った人たちのように研究者の道へ行くか
🪧実践者に戻って、勉強しつつ、保育を先導(ちょっと偉そうな言い方ですが)する道に行くか
歳も歳なので、チャレンジできる機会は減っていき、それが焦りにもなっていました。
しかし、ニュージーランドに行き、そして、その後も色々な保育・教育の現場に行く機会があり、ふと思ったことがありました。
“保育”とはいったいなんなのだろう と。
ニュージーランドでは素晴らしい保育の現場、尊敬できる実践者・研究者に出会うことができました。一方で、社会や大人が求めることに応えるための“サービス”のような保育にも出会いました。それは日本の保育現場でも見たことがあるものでした。
グローバル社会になり、皆が情報を簡単に手に入れられるようになった今、どこかでその情報が操作され、皆が“同じもの”を目指してしまうのではないかと私の中では危惧するところがありました。操作されていなくても、輝かしく“付け加えられたもの”“加工”されたものに惹かれて、皆が同じものを目指してしまうのではないかとも思いました。
私は保育現場も同じようになっている気がします。それが子どもの幸せだと信じ、付け加えることに必死になっていく。理想の子どもに仕上げていくこと、それが保育なのでしょうか。
私は、せめて、乳幼児期は、子どもには子どもらしく過ごしてほしい、と思いました。それが保育なのではないかと思っています。しかし、大人にとって、社会にとって都合のいい人間になるためになってはいないでしょうか。
保育がわからなくなった時、そのヒントをくれたのはやはり“子ども”でした。
加工されず、“与えられた夢中”ではなく、うちからでる“ほんものの夢中”を持って生き生きとしている子ども。そんな子どもに出会うのは、大人の物差しの少ない“自然”のなかでした。それは保育の場で、そして我が子からも感じ取れました。
しかし、私は自然を避けてきた人間(デジタルなど)なので、自然の中で過ごす子どもを“知る”“みつける”ことができないと考えました。
そんな時、浮かんだのが、あるお子さん、そしてそのご家族である“猟師”だったのです(詳しくはWonder journey【加工されていない世界へ】で)
そして、私は“猟師の世界”へ向かい始めたのです。
🪧その⑤ 人として生きる 猟師への道
ニュージーランドの保育に触れて、これからの自分の保育のために猟師の道を目指す。。。とても変な話です。自分でもなぜ“今”この道を歩んでいるのかわからなくなる時があります😅
だからこそ、自分でも『なんでこの道を歩んでいるんだっけ?』となるので、この私の日記である🪧“夢への道標”に綴っておくことにしたのです。
なので、私が狩猟への道を歩んでいる理由を簡単にまとめると、
・グローバルだからこそ輝かしいものばかりに目が生きやすく、同じ“付け加えられた人間”を目指すようになるのではないのか。
・狩猟時代から人間は進化していない。社会の発展とともに、身体や心に弊害を持ち合わせ続けている。社会に合わせて人間づくりになる保育・教育で良いのか。社会のための、社会の弊害を受け止め続ける、保育・教育で良いのか。
・まだ加工されていない子ども(子ども性)が発揮される、物差しの少ない自然の中でいる子ども。その“子どもそのもの”に出会うために、自然とともに生きる猟師に弟子入りする。
と、なります。
私は、これまで人と人とのご縁によって旅を続けてきて、この狩猟への道も偶然というか必然的な出会いによって通っている道です。迷いの時に浮かんだ私の保育の先生ともいえる1人の子ども。そして、その保護者が猟師であったこと。この数奇な、そして貴重な運命の旅路で自分を保育者としてしっかりと育みたいと思っています。
この記事を書いている時点(2025年11月)では、狩猟免許(わな)を無事に取得し、初めての“猟期”を迎えるところです。これから得られる機会を大切にし、そしてこれからの“人生の旅”につなげていきたいです。
終わりに
今回の道標日記では
🪧その1 自分の成長が止まった(自分にとっての都合の良い保育づくり)
🪧その2 ニュージーランドの保育を目指す(もう一度チャレンジ 今の自分を問う )
🪧その3 道標人(みちしるべびと)たちとの出会い
🪧その4 あらためて、“保育”とは?
🪧その5 “子ども”に出会うための猟師への道
私が歩む、“保育とはなんなんだろう”という道。答えなんてない、私なんかが一生かかっても解くことができない問いの道。ただ、ただ、最善を尽くして探り続けたいと思います。子どものための保育者になるために。そして、自分のために。
今回までの“なぜこの道”の記事は後日まとめさせていただきす。
お付き合いいただきありがとうございました。そして、これからも私のWonder Journeyにお付き合いいただければ幸いです。
以上、地図屋でした。
では また👋

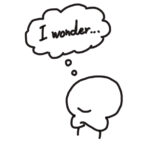
旅する保育者 地図屋のMy Wonder Journeyはコチラ🫱

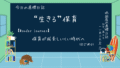
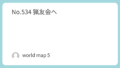
コメント